
納豆とチーズは「タンパク質のなかの王様」
2009.03.11
納豆とチーズは、魚介類、肉類、卵、豆腐などとともに、主に蛋白質を含む食品に分けられる。ともに良質な蛋白質を手軽にとれるすぐれた食品。 納豆は独特な発酵食品 納豆は独特の粘りや香りが特徴となる食品。大... 続きを読む▶▶

2009.03.11
納豆とチーズは、魚介類、肉類、卵、豆腐などとともに、主に蛋白質を含む食品に分けられる。ともに良質な蛋白質を手軽にとれるすぐれた食品。 納豆は独特な発酵食品 納豆は独特の粘りや香りが特徴となる食品。大... 続きを読む▶▶

2009.02.26
空腹感の対処策として、野菜や海藻、きのこなど、たくさん食べてもエネルギーの少ない食品を利用する方法がある。キャベツを使った料理を添えると満腹感を得られやすい。 キャベツは葉がやわらかく味に癖がないので... 続きを読む▶▶

2009.02.26
果物にはビタミンやミネラル、食物繊維、抗酸化物質など、体にとって好ましい栄養成分も多く含まれるが、糖尿病患者には注意が必要な食品。 果物は野菜とともに毎日食べたい食品だが、最近の果物は糖分が多いものが... 続きを読む▶▶

2009.01.29
雑穀を食べる人が増えている。雑穀は食物繊維などが豊富に含まれており、糖尿病患者にとってもメリットの多い食品。 日本人は古来、雑穀を食べていた 雑穀とは、アワ、キビ、ヒエ、ソバ、ライ麦、モロコシなどの穀... 続きを読む▶▶

2009.01.29
味噌汁の具としておなじみのワカメや、コンブ、モズク、ヒジキ、テングサ、フノリなど海藻は古くから日本の食卓で親しまれてきた。 海藻には体の健康を保つ上で大切なはたらきをする食物繊維やミネラルが多く含まれ、エネ... 続きを読む▶▶

2009.01.13
朝食をとらない成人の割合が増加傾向にあることが、厚生労働省の「2007年国民健康・栄養調査」で分かった。朝食欠食は、男性30歳代で約30%、女性20歳代で約25%に上る。 朝食をとらない人は野菜摂取量が少... 続きを読む▶▶

2008.11.25
食事のカロリー摂取量を制限すると、老化が遅くなり、寿命を延びることが、さまざまな研究であきらかになっている。これを受けて米国の「カロリー制限協会」のメンバーたちは、低カロリー食を心がけているという。 こ... 続きを読む▶▶

2008.11.19
高血圧を予防・治療するために食塩を控えることが重要だが、高塩分の食品を食べるときはブドウをいっしょにとると、高血圧や心臓疾患の対策になるかもしれない――ミシガン大学心臓血管センターの研究チームが、ブドウの食品作用につ... 続きを読む▶▶
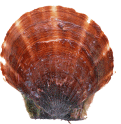
2008.11.13
日本列島の各地で多くの貝塚が見つかっていることからわかる通り、貝は古くから日常でよく食べられている。貝は動物性食品の中では低脂肪で蛋白質が豊富、ビタミンB群など栄養価が高い。最近では貝の食品作用も注目されてい... 続きを読む▶▶

2008.11.07
早食いで満腹になるまで食べる人は、そうでない人に比べ3倍、太りすぎになりやすいことが、日本人3000人以上を対象に行った研究であきらかになった。磯博康・大阪大学公衆衛生学教授らの研究チームが、英国医師会誌「Briti... 続きを読む▶▶

2008.10.24
世界の心臓発作の約30%は、油で揚げた料理や塩分の多いスナック類、肉を多量に食べる欧米型の食事が原因となっているおそれがあるという研究報告が発表された。カナダのマクマスター大学のサリム・ユースフ博士らの研究チ... 続きを読む▶▶

2008.10.20
加工食品や外食を利用するときに「1食にどれだけのカロリーや栄養が含まれるのかを知りたい」と考える人は多い。食事療法を行っている人では特にニーズが高い。 加工食品の包装などには「栄養成分表示」という表示がある... 続きを読む▶▶

2008.10.01
清涼飲料、菓子、菓子パン、ポテトチップスなどの嗜好食品が原則として糖尿病患者に好ましくないとされるのは、これらの食品に砂糖や脂肪が多く含まれる場合が多いから。菓子類の多くは、少量でもカロリー、炭水化物、脂肪が多... 続きを読む▶▶

2008.09.12
「もっとも健康的な食生活」と評された地中海料理の本場で、肥満が急増している。一方で欧米では、日本料理の人気が高まっている。 この40年間に伝統的な食生活が減り、短時間で作れ食べられる手軽なファーストフ... 続きを読む▶▶

2008.08.14
日本人の心疾患の発症がアメリカ人や日系アメリカ人に比べ少ないのは、魚をよく食べているからだとする研究成果が米国で発表された。 魚のn-3脂肪酸で心疾患を予防 この研究は、魚介類からとったn-3脂肪酸と... 続きを読む▶▶
※ヘモグロビンA1c(HbA1c)等の表記は記事の公開時期の値を表示しています。
Copyright ©1996-2025 soshinsha. 掲載記事・図表の無断転用を禁じます。
治療や療養についてかかりつけの医師や医療スタッフにご相談ください。