ニュース
2008年08月14日
魚の多い食事が日本人の心疾患を減らす 米国人の半分以下に
- キーワード
- 食事療法

日本人の心疾患の発症がアメリカ人や日系アメリカ人に比べ少ないのは、魚をよく食べているからだとする研究成果が米国で発表された。
魚のn-3脂肪酸で心疾患を予防
この研究は、魚介類からとったn-3脂肪酸とアテローム性動脈硬化症の発症の関連を調べるために、米ピッツバーグ大学(ペンシルベニア州)の関川暁・公衆衛生大学院助教授らが行ったもので、医学誌「米国心臓学会誌」8月5日号に発表され|
虚血性心疾患 心臓に血液をおくる動脈の硬化や血栓などにより、心臓の血流が悪くなることで起こる疾患で、代表的なものに心筋梗塞があ 大動脈や脳動脈、冠動脈などの太い血管の内膜に、コレステロールなどの脂肪からなるドロドロの粥状物質(アテローム)がたまって粥腫(プラーク)という塊が形成されることで引き起こされる疾患。 プラークが蓄積すると動脈の内腔が狭くなり、心臓や脳などに血液が流れにくくなる。血管内にできるプラークは、ある程度まで大きくなると突然破裂し一挙に血栓を作り、血管内部を塞ぐことがある。これにより心臓では心筋梗塞が起こり、脳では脳卒中が起こる。 動脈硬化が起きても、血管断面積のほとんどが塞がれるまで、自覚症状がないことが多く、元気な人が突然、脳梗塞や心筋梗塞の発作に見舞われてしまうことがある。 |
魚を週1回から2回食べただけで心疾患の予防を期待できる
魚摂取量と虚血性心疾患
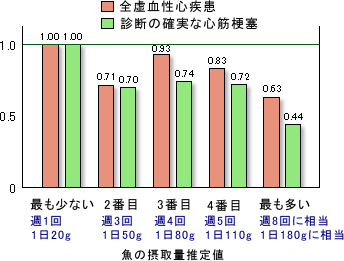
厚生労働省がん研究助成金による指定研究班「JPHC Study」
日本でも、魚のn-3脂肪酸摂取と心疾患の発症との関連を調べた研究が行われている。週1回から2回でも魚を食べることで心疾患の発症予防につながることが、厚生労働省研究班の大規模調査で確かめられ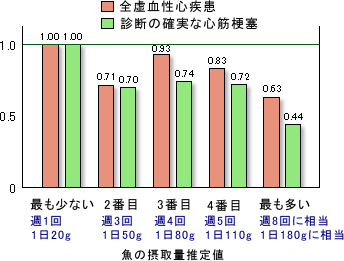
厚生労働省がん研究助成金による指定研究班「JPHC Study」
魚の和風料理はエネルギーを調整しやすい
日本人の魚の消費量は世界でもトップレベルにあるが、年々減少する傾向にある。水産庁の調査によると、魚介類の国民1人1年あたりの平均消費量は、2001年は40.2kgだったのが、2005年は34.4kgに減少した。
食生活などのライフスタイルは50年の間に急激に変化し、20〜40歳代では脂質エネルギー比が適正とされる比率上限の25%を超えている。こうした食生活の変化が、肥満や2型糖尿病、高血圧、脂質異常症などのさまざまな生活習慣病の増加に影響している。 Journal of the American College of Cardiology(英文)
厚生労働省研究班「多目的コホート研究(JPHC研究)」
[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所
食事療法の関連記事

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索