ニュース
2009年01月29日
海藻の栄養 内臓脂肪を減らす効果も
- キーワード
- 食事療法

味噌汁の具としておなじみのワカメや、コンブ、モズク、ヒジキ、テングサ、フノリなど海藻は古くから日本の食卓で親しまれてきた。
海藻には体の健康を保つ上で大切なはたらきをする食物繊維やミネラルが多く含まれ、エネルギー量や脂肪は少ない。さまざまな研究で海藻のもつ力が明らかになってきた。
海藻には体の健康を保つ上で大切なはたらきをする食物繊維やミネラルが多く含まれ、エネルギー量や脂肪は少ない。さまざまな研究で海藻のもつ力が明らかになってきた。
海藻のネバネバ分は食物繊維
海藻は海水中で生育するので、常に海水の塩分や波の衝撃にさらされている。これらから身を守る役目を果たしているのが、海藻の細胞と細胞の間を埋めている「海藻多糖類」と呼ばれるもので、多くは水に溶けてネバネバした粘性のある液体となる。海藻に含まれる多糖質の多くは食物繊維として作用する。ヒトの消化管内で消化や分解されないのでエネルギー源にならない。
食物繊維は、食物が胃や小腸を通過する時間を長くし、炭水化物や脂肪などの吸収を遅くする作用がある。糖尿病患者にとっては、食後高血糖の抑制や、コレステロールの低下という嬉しい作用を期待できる。すぐれた保水性を備えており、腸内物の容積を増大し腸のはたらきを活発にするので、便秘対策にもなる。
海藻にはマグネシウム、ヨウ素、カルシウム、鉄、亜鉛などのミネラルが豊富に含まれる。マグネシウムやヨウ素はコンブなどに多く含まれ、カルシウムはヒジキなどに、マグネシウムはアサオに、鉄分はアオノリに、ビタミンB群はノリに豊富に含まれる。海藻は加工食品であると、ノリの佃煮などのように塩分の多いものが多いので、乾物を上手に利用するのがコツだ。
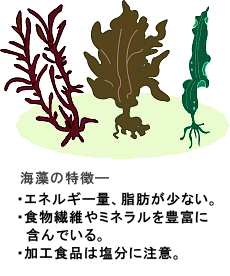
内臓脂肪を減少させる作用も期待できる
佃煮昆布などを製造しているフジッコは2006年3月に、コンブの熱水抽出物に腸管からの糖の吸収を抑制し、血糖値の上昇を抑制する効果があることを動物実験で確かめたと発表した。コンブの熱水抽出物が腸管細胞内からのグルコースの輸送を阻害し、血糖値の上昇を抑えるはたらきをすると考えられてい21世紀COEプログラム「海洋生命統御による食糧生産の革新−海の生物の高度で安全な活用を目指して」 関連情報
糖尿病対策の食事 脂肪少なめで食物繊維は多く
[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所
食事療法の関連記事

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索