
糖尿病の人は腸内細菌が不健康? 野菜を食べると腸内細菌が良好に 腸内環境を改善する2つの方法
2024.07.24
ヒトの腸には、多くの腸内細菌が棲みついていて、「腸内フローラ(腸内細菌叢)」と呼ばれている。腸内細菌が、糖尿病や肥満などと関係があることが分かってきた。 腸内フローラの変化が2型糖尿病を引き起こしている... 続きを読む▶▶

2024.07.24
ヒトの腸には、多くの腸内細菌が棲みついていて、「腸内フローラ(腸内細菌叢)」と呼ばれている。腸内細菌が、糖尿病や肥満などと関係があることが分かってきた。 腸内フローラの変化が2型糖尿病を引き起こしている... 続きを読む▶▶

2024.07.22
糖尿病の人が、睡眠時間が短すぎたり長すぎると、細小血管がダメージを受けやすくなり、深刻な合併症のリスクが高まることが明らかになった。 睡眠時間が一定していない中高年の成人は、2型糖尿病のリスクが高まるこ... 続きを読む▶▶

2024.07.19
夏野菜の代表格といえば「トマト」。さんさんと輝く太陽のもとで育った真っ赤なトマトには、抗酸化作用に富むリコピンなどが豊富に含まれている。 トマトは野菜のなかでも糖質は低めで、血糖値を上げにくい低GI食品... 続きを読む▶▶

2024.07.17
マルチビタミンのサプリメントを利用しても、死亡リスクを低下させる効果はみられないことが、米国の約40万人の成人を20年以上にわたり追跡した調査で示された。 一方で、マルチビタミンのサプリを飲むことで、高... 続きを読む▶▶
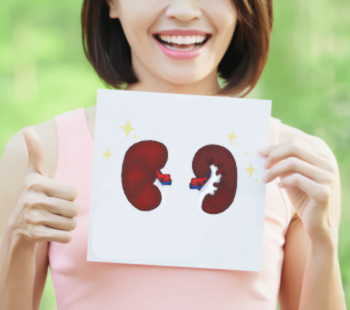
2024.07.16
腎臓病は、糖尿病の合併症のひとつだ。腎臓の機能低下が進行し、腎不全にいたると、透析療法や腎臓の移植が必要になり、生活の質(QOL)は大きく損なわれる。 腎臓病は予防することが大切で、いわゆる「隠れ腎臓病」... 続きを読む▶▶

2024.07.16
糖尿病のある人は血糖値が高い状態が続くと、認知症のリスクが高くなることが知られている。 認知症を予防するために、健康的な生活スタイルは年齢よりも重要という研究が発表された。糖尿病のある人は、血糖管理を良... 続きを読む▶▶

2024.07.11
喫煙は糖尿病のリスクを高めることが知られている。タバコを吸うと血糖値が上昇しやすくなり、糖尿病の合併症のリスクが高まる。 タバコを吸う習慣のある人は、吸わない人に比べ、食事が不健康になりやすいことが... 続きを読む▶▶

2024.07.09
コーヒーを1日に1杯多く飲むだけで、2型糖尿病のリスクが低下するという調査結果が報告されている。 コーヒーを飲む習慣があると、とくに1日に座ったまま過ごす時間の長い人は、心血管疾患が少なく、死亡リスクを... 続きを読む▶▶
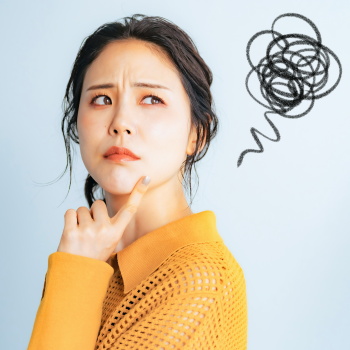
2024.07.08
ストレスは加齢にともない増えるさまざまな健康リスクを高める。ストレスは、体内で炎症を悪化させ、肥満やメタボリックシンドロームのリスクを高めることが分かった。 糖尿病のある人にとってもストレス対策は重要だ... 続きを読む▶▶

2024.07.01
日本の食事スタイルの特徴のひとつは魚を食べること。魚をよく食べている人は、糖尿病のリスクが低く、心筋梗塞や狭心症などの発症が少ないことが明らかになっている。 さらに、小魚を食べる習慣のある人は、死亡やが... 続きを読む▶▶

2024.07.01
「東京糖尿病療養指導士」(東京CDE)、「東京糖尿病療養支援士」(東京CDS)の2024年度の資格審査・受験者用講習会の申込受付が7月より開始されました。 受験者用講習会はeラーニングにより開催されます。... 続きを読む▶▶

2024.06.27
2型糖尿病のある人は、腰痛のリスクが高いことが明らかになった。血糖管理を良好に維持することは、腰痛を予防したり悪化を防ぐためにも必要だ。 最新の研究で、腰痛対策の運動は効果が高いことが分かった。腰痛を経... 続きを読む▶▶

2024.06.26
「酒は百薬の長」ということわざがある通り、ほどよいアルコールはストレス解消やリラックス効果をもたらす。 適度な飲酒は、心臓の健康に良い影響を与え、脳のストレス活動を軽減することが示された。 一方で、... 続きを読む▶▶

2024.06.24
糖尿病ネットワークは、糖尿病のある方とそのご家族に向けて、「糖尿病性腎症」や「慢性腎臓病」についての正しい理解と、その予防と進展防止を目的とした特集コーナー『腎臓の健康道~つながって知る、人生100年のK... 続きを読む▶▶

2024.06.12
5月17日~19日に東京国際フォーラムなどで開催された第67回日本糖尿病学会年次学術集会(会長:植木浩二郎)で、会長特別企画「糖尿病とともに生活する人々の声をきく」が開催された。 このほど同企画の開催報... 続きを読む▶▶
※ヘモグロビンA1c(HbA1c)等の表記は記事の公開時期の値を表示しています。
Copyright ©1996-2024 soshinsha. 掲載記事・図表の無断転用を禁じます。
治療や療養についてかかりつけの医師や医療スタッフにご相談ください。