
朝食を食べないと動脈硬化リスクが2倍に 糖尿病の人に朝食は大切
2017.11.09
朝食を抜く習慣のある人は、朝食をしっかり食べる習慣のある人に比べ、動脈硬化を発症する可能性が2倍に高まるという研究が発表された。 「朝食をしっかり摂ることが、動脈硬化を予防するためにも大切です」と研究者は... 続きを読む▶▶

2017.11.09
朝食を抜く習慣のある人は、朝食をしっかり食べる習慣のある人に比べ、動脈硬化を発症する可能性が2倍に高まるという研究が発表された。 「朝食をしっかり摂ることが、動脈硬化を予防するためにも大切です」と研究者は... 続きを読む▶▶

2017.11.02
「糖尿病の人は、食事でご飯やパンを最初に食べるのは待った方が良いです。食事の順序を調整し、炭水化物を最後に食べると、食後の血糖値の上昇を抑えられます」――ご飯、パン、ポテト、パスタなどの炭水化物を食べるのを... 続きを読む▶▶

2017.11.02
順天堂大学などの研究グループは、2型糖尿病患者が乳酸菌(プロバイオティクス)を摂取すると、腸内フローラが変化し、慢性炎症の原因となる腸内細菌の血液中への移行が抑制されることを明らかにした。2型糖尿病の発症メ... 続きを読む▶▶

2017.11.02
飲酒によって膀胱がんの発症リスクが上昇することが、日本人を対象とした大規模調査で明らかになった。アルコールを飲むと顔が赤くなるのは、アセトアルデヒドを分解する能力が低いからだ。膀胱がんの発症しやすさは、飲酒... 続きを読む▶▶

2017.11.01
今年もあと2ヵ月余りとなった。正月にかかせないおせち料理に、健康に配慮したものが登場している。 紀文は、肥満が気になる人、血糖値が気になる人、糖質制限をしている人などが安心して利用できる「糖質50%オフ... 続きを読む▶▶

2017.10.20
高齢者が日常の生活用品の購入などにも困難をきたす「買物弱者」への対策が大きな社会問題となっている。 買物弱者対策を新たなビジネスチャンスと受け止め、民間業者の参入も目立つようになったが、事業の半数以上が赤... 続きを読む▶▶
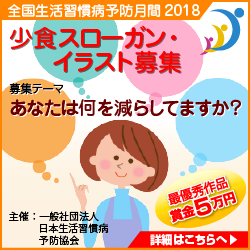
2017.10.19
毎年2月の「全国生活習慣病予防月間」、今回のテーマは、健康標語である一無二少三多の"少食(腹八分目)"にフォーカスし、啓発活動を行います。 食事療法という言葉が糖尿病、脂質異常症、高血圧の予防・... 続きを読む▶▶

2017.10.19
毎年2月の「全国生活習慣病予防月間」、2018年は健康標語"一無、二少、三多"の中から"少食(腹八分目)"テーマとして全国で啓発運動が展開されます。 今年は、より多くのみなさまに健康を意識するきっかけになる... 続きを読む▶▶

2017.10.11
糖尿病治療研究会は、10月3日に東京で「糖をはかる日」講演会を開催した。 10月8日は「糖をはかる日」 ご挨拶 糖尿病治療研究会代表幹事 森 豊 先生(東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・... 続きを読む▶▶

2017.10.10
赤身の牛肉や豚肉や加工肉を食べ過ぎると、糖尿病リスクが上昇することが、アジア人を対象とした大規模調査で判明した。 赤身肉を、魚類、大豆、豆類などに置き換えると糖尿病リスクは減少するという。 赤身肉や加... 続きを読む▶▶

2017.10.10
低カロリー食が寿命を延ばすことはこれまでも報告されていたが、老化のメカニズムに関係する体内時計に影響することが、新たな研究ではじめて明らかになった。 将来はカロリーコントロールで体内時計を制御し、老化を食... 続きを読む▶▶

2017.10.10
食欲を抑えられないのは、脳内で「レプチン」というホルモンの作用が不足しているからだ。 「PTPRJ」という酵素分子が「レプチン」の受容体の活性化を抑制していることを、自然科学研究機構・基礎生物学研究所の研究... 続きを読む▶▶

2017.10.09
第53回欧州糖尿病学会(EASD) 肥満のある2型糖尿病の人は、カロリーを適切に調整した食事と運動を続ければ、糖尿病が「治った」状態を維持できるという研究が発表された。 2型糖尿病に共通する病態 英... 続きを読む▶▶

2017.09.29
魚介を多く食べる人は、そうでない人と比べて、うつ病の発症率がおよそ半分に減ることが、国立がん研究センターや慶応大学などの調査で分かった。青魚に多く含まれる「n-3系脂肪酸」による予防効果が考えられる。 ... 続きを読む▶▶

2017.09.29
第53回欧州糖尿病学会(EASD) 50~60歳の男性は、妻が過体重や肥満であると、自身が2型糖尿病を発症する可能性が高いという調査結果が、欧州糖尿病学会(EASD)学術集会で発表された。 なお、男性が過... 続きを読む▶▶
※ヘモグロビンA1c(HbA1c)等の表記は記事の公開時期の値を表示しています。
Copyright ©1996-2025 soshinsha. 掲載記事・図表の無断転用を禁じます。
治療や療養についてかかりつけの医師や医療スタッフにご相談ください。