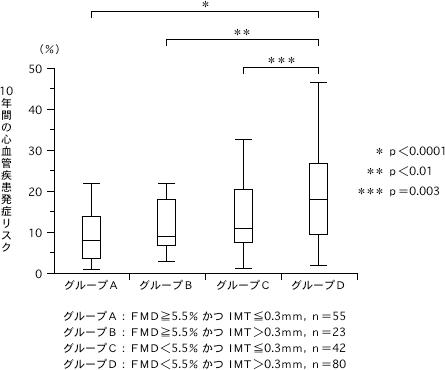ニュース
2013年04月22日
上腕動脈IMT・FMDの同時計測で、冠動脈疾患リスクの層別化が可能
- キーワード
- 糖尿病の検査(HbA1c 他) 糖尿病合併症
血管内皮機能測定に用いられるFMDの上腕計測では上腕動脈のIMTを測定することも可能だが、そのFMDとIMTの測定値を層別化することで冠動脈疾患のリスク評価に役立つとの研究結果が、第77回日本循環器学会学術集会(3月15〜17日・横浜)で報告された。大阪市立大学大学院医学研究科循環器病態内科学・井口朋和氏が発表した。
動脈硬化性疾患の効果的な抑制には、ハイリスク患者への早期介入が重要とされる。現在、介入が必要なハイリスク患者の割り出しに、フラミンガム研究やNIPPON DATEなどの疫学研究データや、頸動脈IMT計測による血管狭窄度などが用いられている。また、動脈硬化の初期に生じる可逆的変化である内皮機能の低下を捉え得るツールとして、FMD(Flow Mediated Dilation)検査も、スクリーニングに汎用されるようになってきた。 FMDは、前腕(または上腕)の駆血-解放による血流依存性血管拡張反応を超音波で計測するもので、測定時には計測動脈のIMTとともに双方をセミオートで測定することが可能。近年、この上腕動脈のIMT(brachialIMT.baIMT)についても、冠動脈危険因子との関連が報告されつつある。
baIMTとFMDは、有意な負の相関関係にある
今回、井口氏らはbaIMTとFMDの両者と、各種臨床指標およびフラミンガムリスクスコアとの相関を検討した。対象は、冠危険因子を有する非冠動脈疾患患者、連続200例。主な患者背景は、年齢59±13歳、男性142名(71%)、喫煙104名(52%)、高血圧93名(47%)、糖尿病66名(33%)、脂質異常症130名(65%)。
まず、FMDを目的変数とし、年齢、性、BMI、喫煙、血圧、eGFR、血清脂質、HbA1c、上腕動脈血管径、baIMTなどを説明変数として重回帰分析を行うと、有意な因子として、年齢(r=−0.233,p=0.01)、上腕動脈血管径(r=−0.303,p=0.0003)のほかに、baIMT(r=−0.356,p=0.002)が残り、baIMTとFMDの有意な負の相関が認められた。
また、baIMTを目的変数とした場合にも、FMD以外の有意な因子として、年齢(r=0.345,p=0.0003)と上腕動脈血管径(r=0.326,p=0.01)が抽出された。
baIMT高値・FMD低値の群ほど、フラミンガムスコアが有意に高い
続いて、baIMTの値で対象を3群に分け、フラミンガムリスクスコア(FRS。10年以内の冠イベント発症率予測)の関係を検討。低位群(baIMT≦0.3mm、n=84)のFRSは11.8±9.5%、中位群(0.3mm<baIMT≦0.4mm、n=94)は15.9±10.5%、高位群(baIMT>0.4mm、n=22)は22.3±11.8%で、baIMTが高い群ほどFRSも有意に高かった(低位群と中位群はp=0.008、中位群と高位群はp=0.01、低位群と高位群はP<0.0001)。
次に、ROC解析により得られた、baIMT0.3mm、FMD5.5%というカットオフポイントでそれぞれを2分し、対象全体を計4群に群分けしたうえでFRSとの関係をみた。すると、FMD高値かつbaIMT低値の群、FMD高値でbaIMT高値の群、FMD低値でbaIMT低値の群、FMD低値かつbaIMT高値の群の順にFRSが高く、群間に有意差があった(図)。
FMD・baIMTとフラミンガムリスクスコアとの関連
|
以上の結果について同氏は、FRSによるリスク評価が欧米人と同程度には日本人においては確立されていないこと、baIMTと冠疾患アウトカムの関係は頸動脈IMTと冠疾患アウトカムとの関連ほどには研究されていないことなど、本研究の限界を挙げたうえで、「上腕でのIMTとFMDの測定は、危険因子を有する非冠動脈疾患患者のリスク層別化に役立つだろう」とまとめている。 1回の測定操作で2つの検査指標を把握できるという臨床上のメリットもあることから、より長期の大規模な研究による有用性の検討が期待される。
◇FMD関連情報:
- FMDは動脈硬化危険因子の集積を鋭敏に反映 CAVI・ABIとの比較
- 食後脂質異常が、食後高血糖よりも血管内皮機能低下に強く影響
- 肥満でEDの中年男性は生活習慣病未発症でも内皮機能が有意に低下
- ACS後の心リハによる運動耐容能向上は血管内皮機能の改善と相関
- DPP-4I追加と併用OHA別にみた内皮機能改善効果 FMDでの検討
- CADでは非糖尿病でも微量アルブミン尿出現率が高く、FMD低下と関連
- 上腕動脈IMT・FMDの同時計測で、冠動脈疾患リスクの層別化が可能
- DPP-4阻害薬の食後高脂血症改善を介した血管内皮保護作用
- 禁煙により酸化ストレスが低下し、血管内皮機能が有意に改善
- 糖尿病細小血管障害とFMD値が相関。短期加療による改善も評価可能
- 血管内皮機能は体温日内変動と相関するが、糖尿病ではその関係が破綻
- 心不全患者の心リハ。急性期のADL改善にも血管内皮機能が関与
- 糖尿病患者の冠疾患スクリーニングにFMDが有用
- 食事由来コレステロールよりはTGとアポB48が血管内皮機能に影響
- 直接レニン阻害薬の多面的効果 透析患者での血管内皮機能を改善
- DPP-4阻害薬の変更による血管内皮機能改善の上乗せ効果
- 塩分の多い食事は、食直後から血管内皮機能(FMD)を低下させる
- 血管内皮機能は血糖変動と逆相関し鋭敏に変化する
- 大豆イソフラボンがTGを低下させ、FMDを改善
- 「血管内皮機能検査」が診療報酬改定で新設される(厚生労働省)
- ミグリトールは冠動脈疾患併発糖尿病患者の血管内皮機能を改善する
- FMD低値は糖尿病発症の予測因子。ドックなどでは精密検査を
- 肥満2型糖尿病では、精神的ストレス軽減が血管内皮機能改善につながる
- 網膜症のある女性糖尿病患者は血管内皮機能(FMD)低下ハイリスク
- HDL-Cの血管内皮機能(FMD)保護作用は糖尿病で相殺される
- 仮面高血圧合併2型糖尿病では血管障害(FMDやPWV)が高度に進展
- DPP-4阻害薬は血管内皮機能(FMD)を改善する
- 脳や心臓の血管が詰まる前に。血管の若返りがわかる検査指標「FMD」
- 動脈硬化が早期にわかるFMD検査装置
- 血管内皮機能、FMD検査のユネクス
- 一般向けサイト 動脈硬化の進展を知る「FMD検査.JP」
[ DM-NET ]
日本医療・健康情報研究所
糖尿病の検査(HbA1c 他)の関連記事
- 針を刺さない血糖測定への挑戦―「超音波」で血糖の状態を知る新技術
- 糖尿病の人の熱中症を防ぐための10ヵ条 猛暑は血糖管理を悪化させる? 十分な対策を
- 減塩食が糖尿病の合併症リスクを低下 塩分を減らすと血圧を下げられる 【おいしく減塩する方法】
- 糖尿病と肥満のある人が体重を減らすとお得がいっぱい たとえ減量に失敗してもメリットが 食事日記をつければ成功率は2倍に
- 肥満のある人が体重を減らすと糖尿病リスクは大幅減少 中年期の体重管理は効果が高い 血糖値を下げる薬を止められる人も
- 糖尿病の合併症を防ぐために「高血糖」と「高血圧」の治療が必要 高血圧があるとリスクは3倍に上昇
- 【笑いが糖尿病を改善】 お笑いライブ鑑賞でストレスが減り楽観性が向上 「笑いヨガ」の効果
- 糖尿病の人は歯を失いやすい 血糖管理が良好だと歯も丈夫に 糖尿病の治療と歯科受診が大切
- 腎臓病は糖尿病の人が発症しやすい合併症 腎臓病の治療は進歩している 透析にならないために
- 糖尿病と高血圧があると腎臓病リスクが上昇 運動時間をわずか5分増やすだけで血圧は低下【高血圧の日】

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索