ニュース
2019年07月25日
循環器領域におけるバイオマーカーとしての尿中L-FABPの有用性と可能性
- キーワード
- 糖尿病の検査(HbA1c 他) 糖尿病合併症
尿中L-FABPはCKDの優れた臨床指標
CKDは末期腎不全のみならず心血管疾患を起こす危険があり、早期発見・治療が重要だが、では何を指標に患者を診ていけばよいのか。患者の予後、治療の妥当性や変更の必要性を常に考えながら診療していくにあたり、血清Crのみでは対応が遅れる可能性がある。その際、CKDの尿中バイオマーカーとして役立つと考えられるのが、L-FABPである。
2型糖尿病患者147例を対象に、糖尿病性腎症の進行を4年間にわたり前向き観察した研究9)では、腎症の病期が進行するとともに尿中L-FABPも上昇し、また非糖尿病のコントロール群に比べると、正常アルブミン尿の段階ですでに値が高いことが示された(図4)。患者を病期進行群と非進行群に分けると、尿中アルブミン、NAG、Type IVコラーゲン、L-FABPで有意に差があったが、実際にROC曲線を描くと尿中アルブミンとL-FABPでROC曲線下の面積(AUC)が高く、診断的価値の高いことが示唆された。
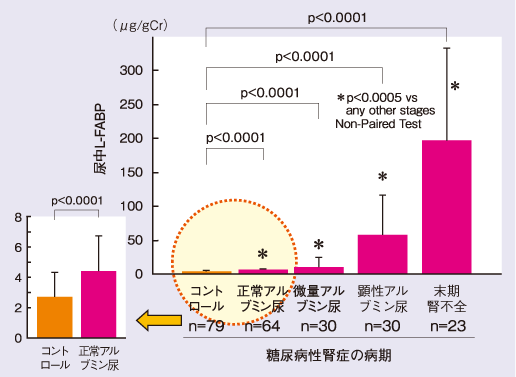
同研究において、尿中L-FABPと尿中アルブミンをそれぞれの基準値(尿中L-FABP 8.4μg/gCr;尿中アルブミン 30mg/gCr)に基づいて組み合わせると4群に分かれる。4年間の経過観察で、両項目とも低い群で腎症が進行する割合は13%なのに対し、両項目とも高い群では70%と、危険性が高いことが示されている。また、尿中L-FABP高値・尿中アルブミン低値の群は50%、尿中L-FABP低値・尿中アルブミン高値の群はわずか9%だった。この結果からも、1つの指標だけでなく複数の指標を組み合わせることが臨床的には重要と考えられる。
2型糖尿病患者618名を12年間追跡した研究10)では、尿中L-FABP高値群(>9.5μg/gCr)の方が、低値群(≦5.0μg/gCr)や中間値群(5.0~9.5μg/gCr)に比べ、透析だけでなく心血管疾患なども含む複合エンドポイントに達する人が多かった。また調整ハザード比をみると、正常アルブミン尿でも微量アルブミン尿でも、尿中L-FABPが高くなるとともにハザード比が上がっており、糖尿病性腎症における予後をみる上で尿中L-FABPが役立つことが示された。
CAG後の尿中L-FABP上昇は長期予後にも関係
尿中L-FABPについてはこのほか、心血管疾患に関する報告もある。CAG後AKIを発症しなかった患者29名を対象に、心血管疾患の発症を10年間にわたり追跡した研究11)では、尿中L-FABPはCAG後12時間・24時間で高値となっていた。患者を10年後までに心血管疾患を発症した群と発症しなかった群に分けると、尿中アルブミンとNAGは両群で差がつかなかったが、尿中L-FABPは発症群で有意に高かった(図5)。Kaplan-Meier法による解析では、CAG前とCAG後24時間の尿中L-FABPの差が11.0μg/gCr以上ある患者では心血管疾患を発症するリスクが高くなっており、CAG後の尿中L-FABPの上昇は、数年から10年後の予後にも関係することが示された。
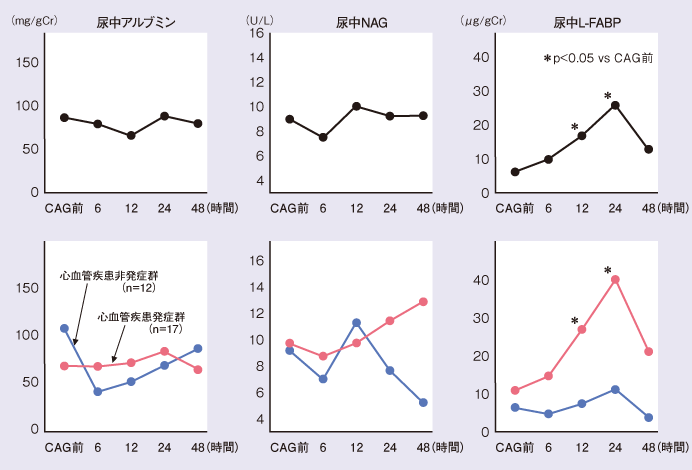
これまで述べてきたように、尿中L-FABPは腎尿細管に対する虚血・酸化ストレスを反映して尿中排泄が増加するため、AKIの発症およびCKDの進展予測のバイオマーカーとして有用と考えられる。また腎障害の進展と関係して、心血管疾患の発症や予後予測のバイオマーカーとしても有用性が示されている。他方、尿中L-FABPは単独で用いるより、尿中アルブミンや他のバイオマーカーと組み合わせること(パネル化)で、臨床的な有用性が増す可能性がある。
今後の課題としては、1つには経過中の値の変化の予後予測における意義や治療の影響が挙げられる。すなわち、もともと値が高い患者を治療した場合どう変化するか、値が下がった患者・経過観察中に上がってくる患者の予後がどうなるかなどについては、まだ十分検討されていない。また、もともとAKIの診断は血清Crの上昇により定義づけられており、尿中L-FABPに基づいてAKIを診断した場合、それが真に予後改善に役立つのかという問題もある。両者を比較した研究はまだ行われておらず、今後の検討が待たれる。
糖尿病の検査(HbA1c 他)の関連記事
- 針を刺さない血糖測定への挑戦―「超音波」で血糖の状態を知る新技術
- 糖尿病の人の熱中症を防ぐための10ヵ条 猛暑は血糖管理を悪化させる? 十分な対策を
- 減塩食が糖尿病の合併症リスクを低下 塩分を減らすと血圧を下げられる 【おいしく減塩する方法】
- 糖尿病と肥満のある人が体重を減らすとお得がいっぱい たとえ減量に失敗してもメリットが 食事日記をつければ成功率は2倍に
- 肥満のある人が体重を減らすと糖尿病リスクは大幅減少 中年期の体重管理は効果が高い 血糖値を下げる薬を止められる人も
- 糖尿病の合併症を防ぐために「高血糖」と「高血圧」の治療が必要 高血圧があるとリスクは3倍に上昇
- 【笑いが糖尿病を改善】 お笑いライブ鑑賞でストレスが減り楽観性が向上 「笑いヨガ」の効果
- 糖尿病の人は歯を失いやすい 血糖管理が良好だと歯も丈夫に 糖尿病の治療と歯科受診が大切
- 腎臓病は糖尿病の人が発症しやすい合併症 腎臓病の治療は進歩している 透析にならないために
- 糖尿病と高血圧があると腎臓病リスクが上昇 運動時間をわずか5分増やすだけで血圧は低下【高血圧の日】

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索