ニュース
2017年07月26日
日常診療におけるバイオマーカーとしての尿中L-FABPの有用性と可能性
- キーワード
- おすすめニュース 糖尿病の検査(HbA1c 他) 糖尿病合併症
運動とL-FABP
次に、運動の話題を取り上げてみたい。かつて腎疾患の治療において運動は推奨されず、むしろ制限することが多かった。しかし現在では腎臓リハビリテーション学会の設立に象徴されるように、運動の重要性が強調されるようになっている。我々も以前、GFRが30mL/分/1.73m2未満という進行したCKD患者であってもL-FABPを上昇させない中等度負荷の運動であれば安全に施行できることを報告している12)。ここでは最近発表された健常者を対象とした筑波大の論文を紹介する。
非CKDの中高年者を運動習慣の有無で2群に分けると、クレアチニンやシスタチンCによるeGFR、尿アルブミンには群間差がなかったが、L-FABPのみ有意な群間差が認められた13)。さらに12週間の有酸素運動を指導したとろころ、血圧の低下とともに腎関連マーカーではやはりL-FABPのみ有意な低下が認められた(図7)。
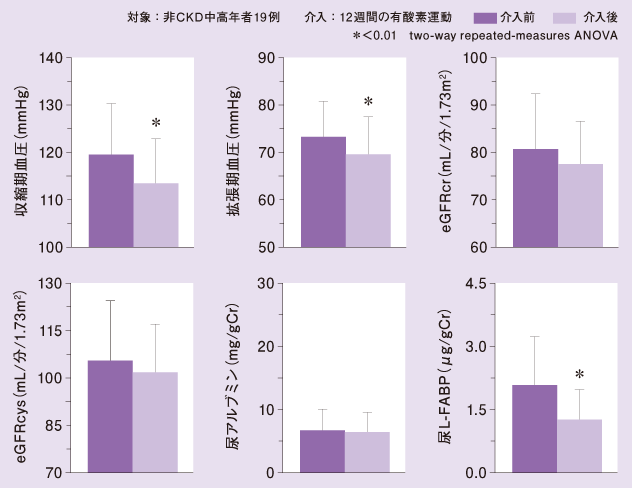
また別の報告では、運動耐容能の指標である最大酸素消費量や握力との関連を検討したところ、その双方と有意な関連があるのは前記3指標のうちL-FABPのみであった14)。腎機能低下と運動耐容能低下のメカニズムの関連を解明する上で興味深い知見である。
L-FABPはAKIの早期マーカーであり、糖尿病その他のCKDで腎障害の進展や生命予後を反映するマーカーである。しかし現時点において、L-FABPを指標とする治療介入が予後改善につながるのか否かという点の検討は十分になされていない。先述のように最近、汎用自動分析装置を用いて院内で簡便にL-FABPを測定できるようなったので、今後より多くの先生方の日常診療にお使いいただき、その臨床の中から新たな知見が集積され、さらに有用なツールとなることを期待している。
参考文献
1) Am J Pathol 178:1021-1032,2011
2) Kidney Int 72:348-358,2007
3) Kidney Int 73:1374-1384,2008
4) Biochem Biophys Res Commun 161:448-455,1989
5) Int J Biochem Cell Biol 33:865-876,2001
6) J Lipid Res 43:646-653,2002
7) Mol Cell Biochem 284:175-182,2006
8) Clin Chem Lab Med 52:537-546,2014
9) Diabetes Care 34:691-696,2011
10) Diabetes Care 33:1320-1324,2010
11) Diabetes Care 36:2077-2083,2013
12) Jpta 45th:Se2-021,2010
13) Scand J Med Sci Sports. 2017 Mar 1. [Epub ahead of print]
14) Clin Exp Nephrol. 2017 Feb 14. [Epub ahead of print]
初 出
第60回日本腎臓学会学術総会
ランチョンセミナー 18 第7会場( 仙台国際センター 会議棟 白檀2)
演題:集中治療における急性腎障害バイオマーカー 〜L-FABPの可能性〜
座長:諏訪部 章 先生(岩手医科大学 医学部臨床検査医学講座 教授)
演者:木村 健二郎 先生(独立行政法人地域医療機能推進機構 東京高輪病院 院長)
共催:積水メディカル株式会社
糖尿病の検査(HbA1c 他)の関連記事
- 針を刺さない血糖測定への挑戦―「超音波」で血糖の状態を知る新技術
- 糖尿病の人の熱中症を防ぐための10ヵ条 猛暑は血糖管理を悪化させる? 十分な対策を
- 減塩食が糖尿病の合併症リスクを低下 塩分を減らすと血圧を下げられる 【おいしく減塩する方法】
- 糖尿病と肥満のある人が体重を減らすとお得がいっぱい たとえ減量に失敗してもメリットが 食事日記をつければ成功率は2倍に
- 肥満のある人が体重を減らすと糖尿病リスクは大幅減少 中年期の体重管理は効果が高い 血糖値を下げる薬を止められる人も
- 糖尿病の合併症を防ぐために「高血糖」と「高血圧」の治療が必要 高血圧があるとリスクは3倍に上昇
- 【笑いが糖尿病を改善】 お笑いライブ鑑賞でストレスが減り楽観性が向上 「笑いヨガ」の効果
- 糖尿病の人は歯を失いやすい 血糖管理が良好だと歯も丈夫に 糖尿病の治療と歯科受診が大切
- 腎臓病は糖尿病の人が発症しやすい合併症 腎臓病の治療は進歩している 透析にならないために
- 糖尿病と高血圧があると腎臓病リスクが上昇 運動時間をわずか5分増やすだけで血圧は低下【高血圧の日】

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索