ニュース
2015年08月17日
糖尿病性腎症の病態と治療〜バイオマーカー・尿中L-FABPの可能性
- キーワード
- おすすめニュース 糖尿病の検査(HbA1c 他) 糖尿病合併症
第58回 日本糖尿病学会 年次学術集会(モーニングセミナー1より)

糖尿病性腎症のマーカーとして従来より、糸球体硬化を反映する尿中アルブミン測定が 用いられている。しかし糖尿病性腎症では尿細管障害も伴うことから、それを捉えること でより早期の介入が可能となる。
本講演では、尿細管障害のバイオマーカーである尿中L-FABPを測定する意義と可能性 を、四方賢一氏(岡山大学病院新医療研究開発センター教授/糖尿病センター副センター長)に講演いただいた。
糖尿病に伴う合併症は大血管障害と細小血管障害に大別される。大血管障害は必ずしも高血糖がなくても起こり得る疾患だが、細小血管障害は高血糖がなければほとんど起こらない。糖尿病特有の合併症と言う場合は後者を指し、糖尿病性腎症もこれに該当する。
糖尿病の治療目的は血糖値を下げることではなく、患者のQOLと寿命を確保することだが、この達成の成否は、QOLを規定する細小血管障害と生命予後を規定する大血管障害の双方をいかに予防するかにかかっている。現在、透析療法導入の原因疾患の第1位が糖尿病性腎症である。ここ数年は増加に歯止めがかかっているものの、年間約1万6,000人、割合にして43〜44%を占めている。QOLと生命予後の双方において、糖尿病性腎症治療に課せられている課題はなお大きい。
糖尿病性腎症とは、古典的には高血糖により糸球体硬化症を来す疾患とされ、病理所見では糸球体の肥大とメサンギウム基質の増加といったびまん性病変が特徴である。これが進行することにより結節性病変や滲出性病変による腎機能が低下する疾患が、狭義での糖尿病性腎症と言える。
この変化が臨床的にどのように現れるのかを表現したのが図1である。GFRはしばらく正常なまま推移するが、比較的早い時期から尿中にアルブミンが漏れ出してきて、それをもって糖尿性腎症の発症を診断する。つまり、アルブミン尿が先行し、後から腎機能が低下してくるというのが典型的な経過とされる。
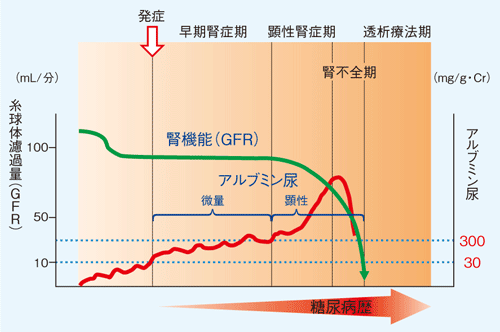
〔槇野博史編著.わかる糖尿病性腎症—診断から透析療法まで, p43. 診断と治療社, 2002〕
尿中に微量なアルブミンが認められる時期を早期腎症といい、その診断には当然ながらアルブミン尿の測定が欠かせない。ところが、定期的にアルブミン尿を測定されている糖尿病患者は意外に少ないと言われている。以前は測定に蓄尿が必須であったことなどがその理由と考えられるが、現在は随時尿を用いクレアチニンで補正した値で診断できるよう簡略化されている。腎症の早期発見のため、より積極的なアルブミン尿測定が望まれる。当院糖尿病外来のデータやJDDM研究から、日本人糖尿病患者の約3人に1人がアルブミン尿陽性であり、そのうちの6割ほどが早期腎症に該当すると推測される。
次は...正常アルブミン尿でありながら腎機能が低下する例も少なくない
おすすめニュースの関連記事
- 【リーフレット公開中】1月23日は「一無、二少、三多の日」
2月1日から「全国生活習慣病予防月間2026」がスタート! - 「糖尿病が強く疑われる人」は推計1,100万人―「国民健康・栄養調査」
- 糖尿病ネットワーク【2025年に多く読まれたニュース トップ10】
- 肥満でない人は糖尿病発症前に体重が減少する傾向にあることを発見
- 【抽選でプレゼント】健康な方の高めのHbA1c対策に!「明治ヘモグロビンA1c対策ヨーグルト」発売記念キャンペーン[PR]
- 歯磨きだけでは不十分?「歯間ケア」が良好な血糖管理に関係する可能性
- 科学的データで見る「ラーメンを食べる頻度」と「健康リスク」の関係
- 糖尿病の人の熱中症を防ぐための10ヵ条 猛暑は血糖管理を悪化させる? 十分な対策を
- 糖尿病の人は「サルコペニア」にご注意 筋肉の減少にこうして対策 何歳からでも予防・改善が可能
- 全ての人に知ってほしい現代医療の必須ワード『SDMって何?』を公開

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索