ニュース
2010年09月07日
iPS細胞で作った膵臓がインスリンを分泌 再生医療の実現へ第一歩
- キーワード
- 医療の進歩
体のあらゆる組織や臓器になる能力のある「iPS細胞(多能性幹細胞)」を用いて、マウスの体内にラットの膵臓をつくることに、東京大学医科学研究所の研究グループが成功した。インスリンを分泌し臓器として正常に機能 することも確かめた。「糖尿病などの再生医療の実現に向けた第一歩」としている。
ラットのiPS細胞使いマウス体内に膵臓
東京大学医科学研究所の中内啓光教授らの研究グループはラットのiPS細胞(多能性幹細胞)から、膵臓をつくりだすことに成功した。この研究は米科学誌「Cell」に9月3日に発表され期待される再生医療の実現
糖尿病性腎症は慢性腎不全の原因の第1位で、糖尿病の増加にともない慢性腎不全患者も増加している。日本透析医学会の調査によると、慢性腎不全で透析療法を受けている患者数は約28万人に上る。透析療法は患者にとって深刻な負担になるだけでなく、年間総額が1兆円を超える治療費が財政をひっ迫させている。
有効な治療として腎移植が考えられるが、日本臓器移植ネットワークによると、2010年8月時点で移植待機者は約1万2000人で、国内で移植療法を受けるのは難しくなっている。
そこで期待されているのが、移植可能な臓器を患者自身の細胞からつくりだす再生医療の実現だ。生体内のすべての細胞に分化ができる多
iPS細胞(多能性幹細胞)から臓器をつくり血糖が正常化
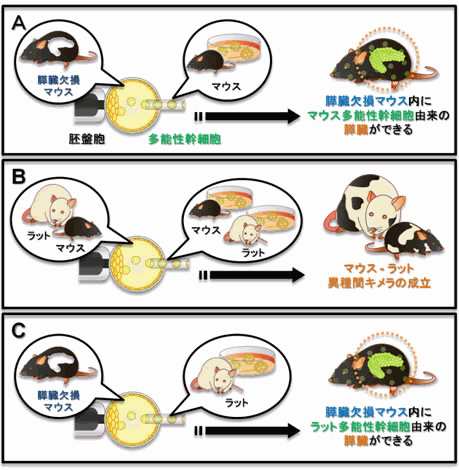
多能性幹細胞を用いてマウスの体内でラットの膵臓を作製することに成功(科学技術振興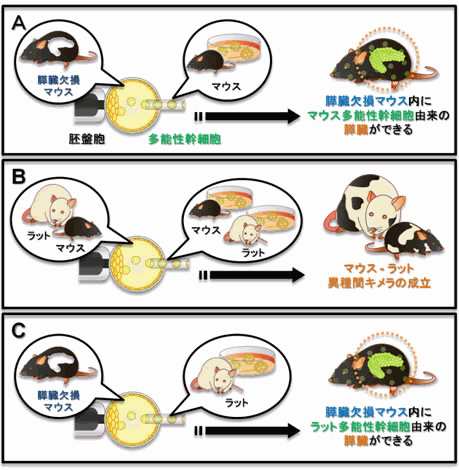
Generation of Rat Pancreas in Mouse by Interspecific Blastocyst Injection of Pluripotent Stem Cells
Cell, Volume 142, Issue 5, 787-799, 3 September 2010
[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所
医療の進歩の関連記事
- 息で糖尿病を検出するセンサーが開発進行中
- 先進医療技術の普及により1型糖尿病患者の血糖管理が大きく改善
- 注射だけでない未来へ「飲むインスリン」研究のいま
- 糖尿病の治療薬メトホルミンが長寿に関係 老化を遅らせ寿命を延ばす薬に期待
- 【1型糖尿病の最新情報】幹細胞から分化した膵島細胞を移植 インスリンが不要になり重症低血糖もゼロに
- 【1型糖尿病の最新情報】発症からインスリン枯渇までの期間を予測 より効果的な治療を期待 日本初の1型糖尿病研究
- 「異種移植」による腎臓移植が最長記録 米国で臨床試験の開始を公表
- 最新版!『血糖記録アプリ早見表2025-2026』を公開
- 腎不全の患者さんを透析から解放 「異種移植」の扉を開く画期的な手術が米国で成功
- 【歯周病ケアにより血糖管理が改善】糖尿病のある人が歯周病を治療すると人工透析のリスクが最大で44%減少

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索