ニュース
2007年04月25日
「高脂血症」を「脂質異常症」にあらため 日本動脈硬化学会が新ガイドライン
- キーワード
- 医療の進歩 糖尿病の検査(HbA1c 他) 糖尿病の診断基準 糖尿病合併症
日本動脈硬化学会は、「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2007年版」を公表した。国内外の臨床研究で得られた新たなエビデンスを取り込み、5年ぶりに改訂した。
新ガイドラインでの主要な変更点は次の通り
- 広く普及している「高脂血症」という疾患名を「脂質異常症」に置き換える方針を打ち出した。
- 総コレステロール値を予防や診療の基準にするのをやめ
た。 - 代わりに、LDLコレステロール(LDL-C)値と、HDLコレステロール(HDL-C)値をそれぞれ別々に設定した。
脂質異常症の診断基準(空腹時採血)
(TG値が400mg/dL未満の場合) |
糖尿病も危険因子
糖尿病は、動脈硬化性疾患の危険因子となる。ガイドラインでは、糖尿病がある場合では、他に危険因子がない場合でも、次の理由で“高リスク”に分類される。
- 2型糖尿病患者数の急増。
- 日本人では脳梗塞よりも少ない冠動脈疾患(心筋梗塞など)の頻度が、糖尿病患者では脳梗塞と同等かそれ以上に高くなる。
- 糖尿病患者の冠動脈疾患を予防するための高血糖改善の効果が、まだ
十分 に確かめられていない。
生活習慣改善の重要性
治療目標については、一次予防(心筋梗塞や狭心症などの動脈硬化性の病気を起こさないための治療)と二次
リスク別脂質管理目標値
日本動脈硬化学会「動脈硬化疾患予防ガイドライン2007年版」より | |||||||||||||||||||||||||||
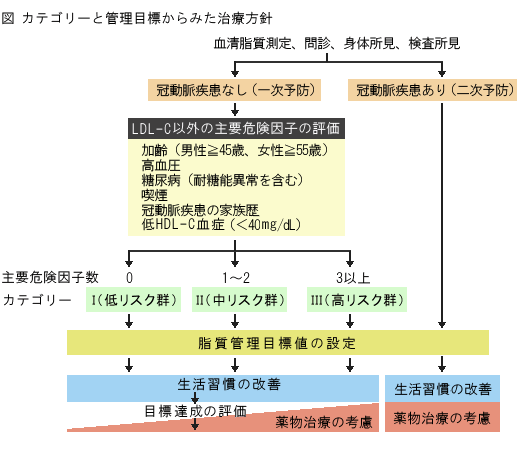
[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所
糖尿病の検査(HbA1c 他)の関連記事
- 針を刺さない血糖測定への挑戦―「超音波」で血糖の状態を知る新技術
- 糖尿病の人の熱中症を防ぐための10ヵ条 猛暑は血糖管理を悪化させる? 十分な対策を
- 減塩食が糖尿病の合併症リスクを低下 塩分を減らすと血圧を下げられる 【おいしく減塩する方法】
- 糖尿病と肥満のある人が体重を減らすとお得がいっぱい たとえ減量に失敗してもメリットが 食事日記をつければ成功率は2倍に
- 肥満のある人が体重を減らすと糖尿病リスクは大幅減少 中年期の体重管理は効果が高い 血糖値を下げる薬を止められる人も
- 糖尿病の合併症を防ぐために「高血糖」と「高血圧」の治療が必要 高血圧があるとリスクは3倍に上昇
- 【笑いが糖尿病を改善】 お笑いライブ鑑賞でストレスが減り楽観性が向上 「笑いヨガ」の効果
- 糖尿病の人は歯を失いやすい 血糖管理が良好だと歯も丈夫に 糖尿病の治療と歯科受診が大切
- 腎臓病は糖尿病の人が発症しやすい合併症 腎臓病の治療は進歩している 透析にならないために
- 糖尿病と高血圧があると腎臓病リスクが上昇 運動時間をわずか5分増やすだけで血圧は低下【高血圧の日】

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索