ニュース
2011年02月28日
全国の糖尿病偏差値を公表 1位は新潟、ワースト1位は鹿児島 厚労省検討会
糖尿病医療の実績値を、全国47都道府県ごとに偏差値であらわした調査結果が公表された。糖尿病の平均偏差値がもっとも高いのは(1)「新潟」、(2)「神奈川」、(3)「長野」の順で、もっとも低いのは(1)「鹿児島」、(2)「徳島」、(3)「沖縄」の順だった。
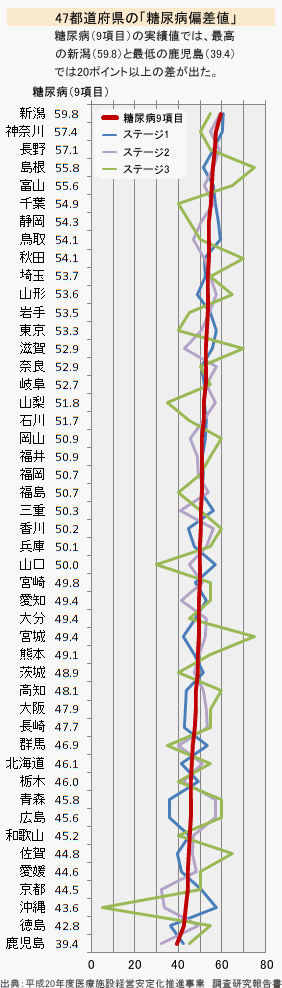
糖尿病偏差値 あなたの県は何位?
厚生労働省の検討会で、糖尿病医療の実績値を全国47都道府県ごとに偏差値であらわした調査結果が発表された。ステージ別(健診、治療・診療、合併症・在宅)の偏差値を示してある。
糖尿病に関連する9項目の偏差値がもっとも高かったのは(1)新潟(59.8)、(2)神奈川(57.4)、(3)長野(57.1)、(4)島根(55.8)の順だった。もっとも低かったのは(1)鹿児島(39.4)、(2)徳島(42.8)、(3)沖縄(43.6)、(4)京都(44.5)の順だった。
糖尿病の9項目とは、「年齢調整受療率(男女)」、「年齢調整受療率(女)」、「基本健診受診率」、「年齢調整受療率(高血圧・女)」、「医療機能情報公開率(病院)」、「医療機能情報公開率(診療所)」、「退院患者平均在院日数(糖尿病)」、「新規透析導入」のこと。
医療機関など地域の医療提供体制の整備を促すことを目的に、都道府県は「医療計画」を策定し、5年ごとに見直している。医療計画は1980年代の医療法改正で創設された。医療機関間の機能連携をスムーズに行えるようにし、適切な治療を切れ目なく受けられる医療の実現、地域の医療資源の効率的な活用を目指している。
糖尿病は医療計画で重視されており、4疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病)5事業(救急医療、小児医療、周産期医療、災害医療、へき地医療)のひとつに含まれている。
ステージ別にみると、都道府県別の偏差値で特に大きく差が出たのはステージ3の「合併症・在宅」だ。合併症発症率や糖尿病性腎症による新規透析導入、糖尿病網膜症による視覚障害などの実績値を調べ、「どのくらい重い合併症になるのか」を示したところ、偏差値がもっとも高い島根と宮城(それぞれ75)に比べ、岩手、福島、茨城、千葉、東京、栃木、静岡、和歌山、石川、大分、鹿児島が40台、群馬、山梨、山口が30台となっている。
その他、報告書では千葉、東京、静岡、大阪、鹿児島を対象に行った調査実施の結果や、各都道府県の医療計画や医療連携を含めた具体的な実績(ヒアリング)も示された。
糖尿病の病診連携
患者に分かりやすい情報公開も必要
人口増加や高齢化、生活スタイルの変化などの影響を受け、2型糖尿病などの生活習慣病は増えている。糖尿病が強く疑われる人や可能性を否定できない「予備群」は合計2210万人と推計されており、10年前の1997年に比べ840万人も増加した。また、糖尿病と関連の深い心臓病(虚血性心疾患)や脳卒中など命にかかわる深刻な病気への治療介入もますます重要になっている。
患者数が急増するにつれ、専門の高度な医療機関のみで診療するのは難しくなり、また地域の医療機関の外来治療のみで対応するのも限界が出てきた。そこで、糖尿病患者の重症化を防ぐため、複数の医療機関で1人の患者の治療方針などの情報を共有する「病診連携」という仕組み作りが進められている。
主治医が専門治療が必要な糖尿病患者を基幹となる病院に紹介し、その後フォローアップしながら適切な時期に診療所の主治医のもとに再び送るのが一般的な病診連携だ。複数の医療機関が協力しあうことで、きめ細かい治療を続けられ、必要な時期に適切な診療を受けられる環境を実現できると考えられている。
厚労省の検討会では「患者の視点に立つと、制度自体が分かりやすく示されていない」という課題が示された。患者や家族にとっても、「地域の保健医療提供のが現在どうなっているのか」、「今後はどう変わっていくのか」といった、都道府県が策定する医療計画を知ることは重要だ。
厚労省検討会でも、住民に医療機関や医療内容についての情報を分かりやすく伝え、医療の現状について理解を促すための方策を進める必要性が強調された。
第2回医療計画の見直し等に関する検討会(厚生労働省、2011年2月18日)患者に分かりやすい情報公開も必要
第3回医療計画の見直し等に関する検討会(厚生労働省、2011年2月28日)
47都道府県の糖尿病医療のステージ別実績値
- 平均値
偏差値が最も高いのは新潟で59.8、以下、神奈川57.4、長野57.1、島根55.8の順となっており、最も低いのは鹿児島で39.4、以下、徳島42.8、沖縄43.6、京都44.5の順となっている。 - ステージ1:健診
<構成指標>
- どのくらい多いか(り患率 受療率 患者数)
- どのくらい関心があるか(基本健診受診率 健診受診者数)
- どのくらい関心があるか(精密検査受診率 検診受診者数)
ステージ1:健診は、年齢調整受療率(男)、年齢調整受療率(女)、基本健診受診率、年齢調整受療率(高血圧・男)、年齢調整受療率(高血圧・女)、の5つの指標で構成されている。
<全指標が偏差値50以上>
5つの指標がすべて偏差値50以上となっているのは、千葉、長野、静岡、三重、滋賀、の5県であり、地域的な傾向として、東海・近畿地方が多い。
<全指標が偏差値50未満>
5つの指標がすべて偏差値50未満となっているのは、青森、広島、愛媛の3県であり、地域的な傾向として、中国・四国から2県が該当している。↓ - ステージ2:治療・診療
<構成指標>
- どのくらい健康に留意しているか(ハイリスク群の減少率 受療率(高血圧) 患者数)
- どのくらい健康に留意しているか(ハイリスク群の減少率 受療率(高脂血症) 患者数)
- どこに行ったらよいか(医療機能情報公開率 インターネットに医療情報を掲載している医療機関数/医療機関数)
ステージ2:治療・診療は、医療機能情報公開率(病院)、医療機能情報公開率(診療所)、退院患者平均在院日数(糖尿病)、の3つの指標で構成されている。
<医療機能情報公開率(病院)>
偏差値が最も高いのは岩手、宮城、秋田等の26県で54.9、最も低いのは京都で7.3、以下、沖縄14.0、岡山32.5、栃木35.1の順となっている。
<医療機能情報公開率(診療所)>
偏差値が最も高いのは宮城、千葉、新潟、島根、福岡の5県で61.6、最も低いのは群馬で16.7、以下、滋賀22.4、愛知22.8、栃木37.0の順となっている。
<退院患者平均在院日数(糖尿病)>
偏差値が最も高いのは長野で62.6、以下、山形62.4、新潟61.8、静岡60.9の順となっており、最も低いのは鹿児島で14.1、以下、福岡31.0、三重32.4、徳島36.7の順となっている。地域的な傾向として、東日本が高く西日本が低い。↓ - ステージ3:合併症・在宅
<構成指標>
- どのくらいで日常生活に戻れるか(総治療期間 外来受診回数平均診療間隔から算出)
- どのくらい重い合併症になるのか(合併症発症率 新規透析導入率 糖尿病性腎症による新規透析導入患者)
- どのくらい重い合併症になるのか(合併症発症率 視覚障害り患率 糖尿病網膜症による新規視覚障害者数)
ステージ3:合併症・在宅は、新規透析導入率で構成されている。
<新規透析導入率>
偏差値が最も高いのは宮城、島根で75.0、次いで秋田、滋賀で70.0、最も低いのは沖縄で5.0、以下、山口30.0、次いで群馬、山梨で35.0の順となっている。 - 相関図 「?.糖尿病」
<実績値・採用率とも偏差値50未満>
実績値・採用率とも偏差値50未満となっているのは、青森、群馬、広島、高知、長崎、宮崎、沖縄の7県となっている。地域的な傾向として、九州地方など西日本が多い。
平成20年度医療施設経営安定化推進事業(各都道府県の新たな医療計画にかかる調査研究) 調査研究報告書
都道府県より提供された医療機関の情報を検索できるサイト。2009年4月から本格施行された「医療機能情報提供制度」では、患者が地域の医療機関が提供する治療などの情報を知ることができる仕組みが考えられている。
[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所
糖尿病合併症の関連記事

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索