ニュース
2009年02月27日
血管障害の「残された危険因子」を探る国際プログラム「R3i」がスタート
- キーワード
- 糖尿病合併症
現在、先進諸国における死亡原因として、心筋梗塞や脳梗塞などの血管障害に基づく疾患が大きな位置を占めている。わが国も例外でなく、死亡原因の第2位が心疾患、第3位が脳血管疾患であり、両者を合計すると日本人の約3割が心血管疾患で死亡していることがわかる。
これらの心血管疾患、とくに大血管障害(動脈硬化)の発症・進展を抑止するために、その主要危険因子と考えられるLDLコレステロールに対し、現在ではスタチンを中心とする脂質低下療法が広く行われるようになった。実際それにより動脈硬化性疾患の発症リスクが減少することは、すでに数々の大規模スタディが証明している。
る。
糖尿病がある場合、動脈硬化性疾患を発症する以前ですでに、心筋梗塞の既往歴のある非糖尿病の患者さんと同程度にイベント発生の危険が高くなっていることを示した報告もあり、「残された危険因子」を見出し治療することがより重要とされる。また糖尿病では大血管障害による生命予後の悪化だけでなく、細小血管障害による網膜症、腎症などもQOLを低下させる要因として見過ごすことができず、それらに対する治療戦略もまだ未解決の課題が残されている。
。
関連情報
R3iの公式ページ(英文)
糖尿病性血管障害のより確実な抑止のために(糖尿病NET)
スタチンだけでは心血管障害を防ぎ得ない
しかし、近年登場した強力なスチタンを用いLDLコレステロール値を下げても、動脈硬化性疾患を確実に抑止できるとは言い難い。例えば、海外でアトルバスタチン80mg/日という高用量(国内では重症の家族性高コレステロール血症に対する最大用量が40mg/日)を用いて行われたスタディでは、同薬を10mg/日 用いた場合に比べて心血管イベント発生の相対リスクが6年間で22%減った一方で、78%に心血管イベントのリスクが残され、8.7%の心血管イベントが発生した。このことは、動脈硬化性疾患を確実に抑えるには、LDLコレステロール値の管理だけでは不十分であり、なんらかの「残された危険因子」があることを示してい
スタチンによる脂質低下療法に「残された危険因子」
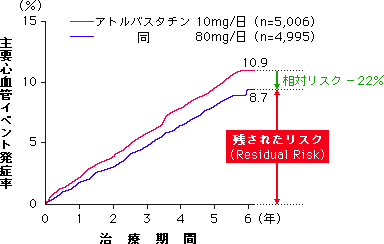
N Engl J Med 352: 1425-1435, 2005
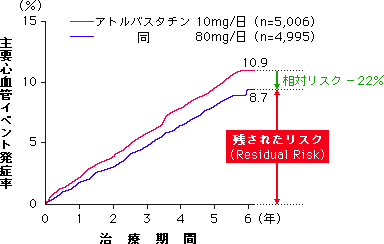
N Engl J Med 352: 1425-1435, 2005
想定されている「残された危険因子」
血管障害の「残された危険因子」はなにか?
その答えを探るために、「R3i(Residual Risk Reduction Initiative)」という世界的な取り組みが2008年にスタートした。これは世界40ヵ国で指導的な立場にある心疾患や内分泌領域の専門家が参加し、心血管疾患と細小血管障害について国際的な調査を進めるプログラムである。運営委員の一人として日本からは門脇孝氏(東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科教授)が参画している。
高LDLコレステロール血症以外の危険因子としては現在、高トリグリセライド血症(とくに食後高トリグリセライド血症)、低HDLコレステロール血症、small dense LDLなどが知られており、これらへのアプローチもR3iプログラムの研究課題になるものと想定される。
近年、血管障害の強力なリスクファクターとなり得る糖尿病やメタボリックシンドロームの患者数が先進国のみならず、アジア諸国でも急増しており、その予防と適切な治療の普及が急務となっている。同プログラムが結実し、より効果的かつ確実な血管障害抑止の戦略が確立されることが望まれるR3iの公式ページ(英文)
糖尿病性血管障害のより確実な抑止のために(糖尿病NET)
[ DM-NET ]
日本医療・健康情報研究所
糖尿病合併症の関連記事

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索