ニュース
2015年10月23日
内臓脂肪肥満を解消すれば健康寿命を伸ばせる 肥満症予防協会
- キーワード
- メタボリックシンドローム 糖尿病と肥満 運動療法 食事療法
一般社団法人 日本肥満症予防協会は10月9日に日比谷コンベンション大ホール(東京)で、特別事業「内臓脂肪肥満を解消して健康寿命を伸ばそう」を開催した。

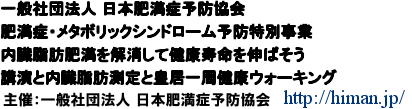
基調講演「内臓脂肪肥満解消と健康生活」
松澤佑次 氏(日本肥満症予防協会理事長、住友病院院長)
松澤佑次 氏(日本肥満症予防協会理事長、住友病院院長)


肥満を改善することで多くの健康障害を取り除ける
「肥満の人を放置せず、疾患が伴えば肥満症という病気として診断し、重症化する前に治療することの大切さを認識してもらいたい」と、松澤氏は言う。
沖縄はかつては長寿県日本一を誇り、世界が賞賛したほどの健康長寿県だった。しかし、2000年に都道府県別平均寿命で沖縄県男性の平均寿命が26位に転落。同県の健康長寿の危機的状況は「沖縄クライシス」として、各方面で大きな衝撃が広がった。
沖縄の肥満者の割合は全国に比べ男女とも全年齢で高い。車社会になり移動を車で済ませ運動不足が常態化していることや、食事の摂取エネルギーが増加し、特に脂質を摂り過ぎていることなどが要因だ。沖縄では現在県を上げて肥満対策に取り組んでいる。
肥満は糖尿病や高血圧、高脂血症などの生活習慣病の発症に大きく関与している。「日本ではBMI(体格指数)25以上が肥満とされ、BMI基準による高度肥満者が少ないにも関わらず、2型糖尿病などの発症は欧米に匹敵する」と、松澤氏は指摘する。
松澤氏らが提唱した「メタボリックシンドローム」(内臓脂肪症候群)などの研究で、日本は今や世界をリードする成果を挙げている。その概念を柱にした厚生労働省の特定健診・保健指導は予防医学の実績を積み重ねている。
肥満症の研究でもうひとつ注目されているのは、松澤氏ら大阪大学の研究グループが発見した「アディポネクチン」だ。アディポネクチンは内臓脂肪組織から分泌されるホルモンだ。
アディポネクチンには、傷ついた血管壁を修復する働きをしていて動脈硬化を予防するほか、インスリンの働きを高める作用、血圧を低下させる作用などがある。内臓脂肪が増えると、アディポネクチンの分泌が減少し、動脈硬化を防ぐ働きが低下し、インスリン抵抗性の状態を引きおこし、血糖を上昇させる。
アディポネクチンは肥満症の研究において、生活習慣病のカギになるバイオマーカーとして世界的に評価されている。「健診などでのアディポネクチンの測定を積極的に進めるとともに、アディポネクチンを増やす治療法の開発も肥満症対策として重要になっている」と、松澤氏は言う。
特別講演「食べ方と運動 治す・防ぐ・若返る健康生活」
中村丁次 氏(日本肥満症予防協会 理事、神奈川県立保健福祉大学 学長)
中村丁次 氏(日本肥満症予防協会 理事、神奈川県立保健福祉大学 学長)

「特定健診・特定保健指導」は世界に誇れるリスクマネジメント
2008年に開始された「特定保健指導」では、生活習慣病の発症リスクが高い人に対して、医師や保健師や管理栄養士などが1人ひとりの身体状況に合わせた生活習慣を見直すためのサポートが行われている。特定保健指導には、リスクの程度に応じて「動機付け支援」と「積極的支援」がある。
厚生労働省の作業部会は、「特定保健指導」による検査値への影響と医療費の適正化効果について経年的な分析を実施し、中間結果を公表した。
それによると、特定保健指導を受けた人は、血糖や血圧、中性脂肪などの検査値の改善効果が3年間続いたことが判明した。積極的支援を受けた参加者は、2008年度と比べて2011年度では、男女ともに腹囲と体重がそれぞれ減少した。
また調査では、メタボリックシンドロームの人が併発しやすい高血圧症と脂質異常症、糖尿病に関連する入院外医療費などの推移も、参加者と不参加者とで比較した。参加者の方が医療費が低く抑えられることが明らかになった。
2009年の1人当たり入院外保険診療費は、積極的支援の参加者では不参加者に比べ、男性で5,340円、女性で7,550円少なかった。
メタボリックシンドローム(内臓肥満)に焦点を当て、食事や運動の行動変容を促す「特定健診・特定保健指導」は、健康障害を予防し医療費を抑制する、世界に誇れるリスクマネジメントの手法だ。
「介護や寝たきりではなく、人の手をかりずに自立して健康的に長生きできるよう健康寿命を延ばして行くことが高齢社会を支える大事なポイントです。そのためには健康的な食事をおいしく、楽しく続けることが大切です」と、中村氏は強調している。
「ウォーキングの効果と歩き方」
木谷道宣 氏(木谷ウオーキング研究所 所長)
木谷道宣 氏(木谷ウオーキング研究所 所長)

[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所
メタボリックシンドロームの関連記事
- 体重をわずか3%減らすだけで肥満・糖尿病を改善できる 【日本肥満症予防協会セミナー・レポート】
- 糖尿病や肥満の新たな治療 肝臓の「アクチビンE」が脂肪を燃焼
- 糖尿病と心不全リスク 「心不全パンデミック」に3つの方法で対策
- 甘いものを食べるなら日中の活動時間を選ぶとメタボになりにくい
- 「職場ストレス」がメタボの危険性を40%上昇 ストレスを解消
- 対談「女性と生活習慣病予防」一無、二少、三多で健康長寿
- 「ミドリムシ」から糖尿病を改善する成分 「痩せるホルモン」を促進
- 「やせ過ぎ」「人とのつながり」「喫煙」が高齢者の寿命を縮める
- 「おにぎりダイエット」で体重が減少 ご飯と運動で腹囲は減らせる
- 特定保健指導の効果を「ビッグデータ」で検証 メタボが31%減

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索