ニュース
2010年04月26日
塩分とりすぎ どう防ぐ? 日本は「減塩後進国」
- キーワード
- 食事療法
食塩を控えることは、高血圧や脳卒中、心筋梗塞を予防・治療するうえで重要。糖尿病腎症を予防 するためにも、塩分を控えることが勧められている。しかし、減塩が望ましいことを多くの人が知っていても、実行するのはなかなが難しい。



おいしく無理なく減塩するコツ
日本食は生食や素材の味をいかし、多彩な味を楽しめるのが特徴。管理栄養士に毎日の食事での減塩のコツを教えてもらったところ、「薄味に慣れる」「漬け物・汁物の量に気を付ける」「塩味を効果的に使う」の3点を教えてくれた。
- だしの風味をいかす
かつお節や昆布、煮干、シイタケなど天然食品からとっただしの旨味をいかせば、塩やしょうゆを減らしてもおいしく食べられる。 - 酸味を利用
穀物酢、レモン、ゆず、かぼすを利用し、酢物や和え物にすると薄味でおいしく食べられる。 - 香辛料を利用
辛子、唐辛子、こしょう、さんしょう、わさび、ごまなどを利用し、味付けにアクセントを加える。 - 香味野菜やハーブをとりいれる
香味野菜を味付けのアクセントにする。生姜、ねぎ、しそ、パセリ、大根おろし、かいわれ大根、三つ葉、にんにくなどを、薬味や付け合せやとして利用。 - しょうゆはかけないでつける
しょうゆなどで味付けするときは、表面につけると、味をしっかり感じられ薄味が気にならない。 - 味噌汁は具を多くする
味噌汁1杯に1.5〜2gの塩分が含まれる。汁物に野菜や海藻、こんにゃく、豆腐などの具を多く入れると、汁が少なくなり塩分を減らせる。野菜をたっぷりとれ、満腹感も得られやすい。 - 減塩しょうゆを利用
「減塩しょうゆ」や「減塩だしつゆ」を使えば、細かい調味料の調節の手間を省き、無理なく減塩できる。
-
食塩相当量を知る方法
加工食品などの成分表示には、ナトリウム量が
表記 されているが、食塩相当量は記されていないことが多いので分かりにくい。食塩相当量は次の式から求められる。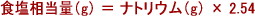
-
日本人の食塩摂取目標量は「男性9g未満、女性7.5g未満」
厚生労働省がまとめた「日本人の食事摂取基準(2010年版)」で、食塩相当量の1日摂取目標量が「男性9g未満、女性7.5g未満」と、より厳しく引き下げられた。それまでは食塩摂取量を1日10g未満とされていたが、約30年ぶりに改定された。

「日本人の食事摂取基準」(厚生労働省)
日本の食文化と塩は密接に結びついており、日本人の食塩摂取量は海外に比べると大幅に多い。
食塩を急に減らすと他の栄養素にも悪影響を及ぼすおそれがあるという考えから、これまでは「無理な減塩は注意した方が良い」とされていた。
一方、海外の基準では血圧値を上昇させない食塩摂取量の平均値は3〜5g/日と考えられており、日本高血圧学会ガイドライン(JSH2009)でも食塩摂取量として6g/日未満を勧めている。
日本人の食塩摂取量は少しずつではあるが、年々減ってきている。最近の調査では従来の目標量をほぼ達成している。そこで、「食塩摂取量はできるだけ少ない方がよいので、新たな目標量が必要」と、より低い値が設定されることになった。
「日本人の食事摂取基準」(2010年版)(厚生労働省)
食品成分表を使った栄養成分の計算方法(農林水産省)
お塩ひかえめ家族のためのカンタンヘルシーレシピコンテスト(クックパッド)
[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所
食事療法の関連記事

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索