ニュース
2008年07月30日
乳製品からカルシウムをよくとる人は脳卒中が3割減少
- キーワード
- 食事療法

カルシウムの摂取量が多い人は脳卒中になりにくいことが、厚生労働省研究班の大規模調査で分かった。カルシウムを多くとる人は、ほとんどとらない人に比べ、脳卒中の発症率が3割ほど低いという。
研究班は、岩手、秋田、長野、沖縄の4県在住の40歳から59歳の男女約4万人を対象に、1990年から2002年まで追跡調査を行った。 研究開始時とその5年後に実施した食事など生活習慣についてのアンケート調査から、総カルシウム摂取量、牛乳・チーズ・ヨーグルトなどの乳製品からのカルシウム摂取量、大豆製品・野菜などからのカルシウム摂取量を推定した。
乳製品からのカルシウム摂取量と
脳卒中発症との関係
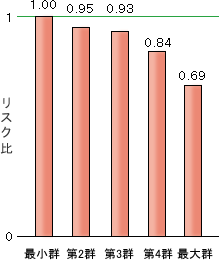
厚生労働省研究班
「多目的コホート研究(JPHC研究)」
その後約13年の追跡期間中に発症した脳卒中や虚血性心疾患との関連を調べた。期間中に1321人が脳梗塞や脳出血などを発症した。
脳卒中発症との関係
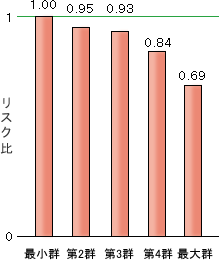
厚生労働省研究班
「多目的コホート研究(JPHC研究)」
カルシウムで脳卒中リスク3割減
乳製品から取ったカルシウムの量で5グループに分け解析したところ、1日の摂取量がもっとも多いグループ(平均116mg)は、もっとも少ないグループ(同0mg)に比べ、脳卒中の発症率が0.69倍と低かった。
また、総カルシウム摂取量でも、もっとも多いグループ(同750mg)でも、もっとも少ないグループ(同230mg)に比べ、発症率が0.70倍になり、同様に低かった。
大豆製品や野菜、魚など、乳製品以外から摂取したカルシウムと発症の関連については、あきらかな効果はみられなかった。また、心筋梗塞など心疾患の発症率は、カルシウム摂取量との関連はみられなかった。
1日130mlの牛乳で脳卒中予防の効果を期待できる
食品でとれるカルシウム量の目安
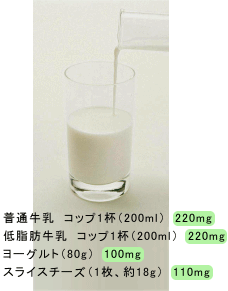
脳卒中は日本人の死因第3位の病気で、糖尿病の人では特に発症率が高い。研究班は研究成果について、次のように話している―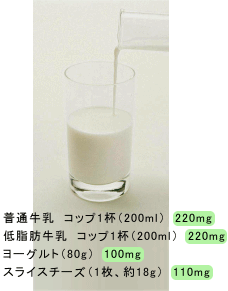
- カルシウム摂取量が多い人は、少ない人に比べ、血圧が低くなることが他の研究でもあきらかになっている。
また、血圧値だけでなく血小板の凝集やコレステロールの吸収を抑えることも報告されている。これらが脳卒中予防につながったと考えられる。 - カルシウム摂取と心疾患の関連がみられなかったのは、乳製品にはカルシウムの他に飽和脂肪酸も多く含まれるからだと考えられる。
飽和脂肪酸は、虚血性心疾患など動脈硬化性の血管障害リスクを上げるので、カルシウムの効果を打ち消してしまうおそれがある。
関連情報
牛乳の栄養が見直されている
[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所
食事療法の関連記事

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索