ニュース
2014年03月19日
魚の和風料理はエネルギーを調整しやすい 食事療法に活用
- キーワード
- 食事療法
魚は糖尿病の食事療法で上手に活用できる食材だ。魚料理の多くはエネルギーは少なめで、良質な蛋白質を含んでいる。体に良いEPAやDHAといったn-3系脂肪酸(オメガ3脂肪酸)も含まれる。
 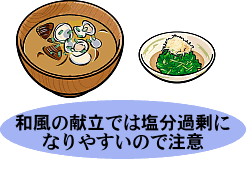  |
知っておきたい「魚を食べるメリット」
魚料理が体に良いとされる理由として、大きく次の2点がある――
- コレステロールを下げるはたらきなどがあることから摂取を増やすべき栄養素とされる、不飽和脂肪酸の一種である「n-3系脂肪酸」を豊富に含んでいる。
- カルシウム吸収に必要なビタミンDが豊富に含まれている。
魚の揚げ物には注意
揚げ物は、から揚げ、天ぷら、フライとあるが、どれも衣が多いほど吸油率が高くなり、高エネルギーになる。素揚げ<から揚げ<天ぷら<フライという順に衣が厚くエネルギーが高くなる。食べる回数や量を減らすのが無難だ。
表面積が大きいほど衣の量も増えるので、魚の揚げ物では材料をなるべく大きく切るのがコツとなる。また、揚げる時間が長いと、それだけ衣が油をたくさん1人当たりの魚の摂取量は年々減っている
水産庁の調査によると、日本人が食べる魚の量は減少している。魚介類の国民1人1年あたりの平均消費量は、1995年は96.9kgだったのが、2009年には74.2kgに減少した。

[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所
食事療法の関連記事

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索