ニュース
2007年06月12日
日本人の栄養バランス 45年の変化
- キーワード
- 食事療法

毎年6月は「食育月間」。各地で市民公開講座などの関連したイベントが開催される。2型糖尿病などが増加した一因として食習慣の乱れが挙げられている。この機会に日本人の食事が年を追うごとにどのように変化したかを、もう一度みてみよう。
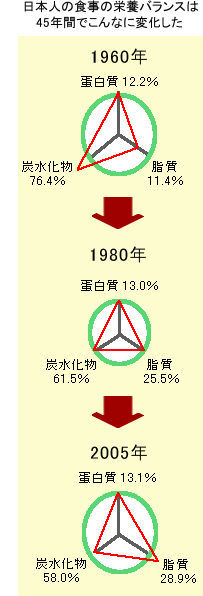
厚生労働省資料
|
日本人の栄養バランスは1980年頃は良かった
栄養素の適正な配分は、エネルギー量の50〜60%を炭水化物をから、15〜20%を蛋白質から、20〜25%を脂質からとるのが適正とされる。
平均的な日本人の食事は、1960年頃は炭水化物が75%以上で、脂質は12%未満だった。1980年頃になると、日本の気候風土に適した米を中心に水産物、畜産物、野菜などのさまざまな食品から構成され、栄養バランスに優れた「日本型食生活」が実現していた。
しかし現在では、脂質の過剰摂取、野菜の摂取不足など栄養の偏りがみられるようになってきた。厚労省の2005年調査によると、脂質摂取のエネルギー比は28%を超えている。
その結果、BMI(肥満指数)が25以上の肥満者は、男性の40歳代で34%、女性でも60歳代で29%と高い割合になっている。肥満と関わりの深い2型糖尿病の患者と予備群を合わせた割合も、男性の50歳代で24.7%、60歳代で31.3%、女性の60歳代で27.5%と高い。
栄養バランスの偏りやエネルギーの過剰摂取は、日本だけでなく、欧米やアジア諸国など世界中で問題になっている。
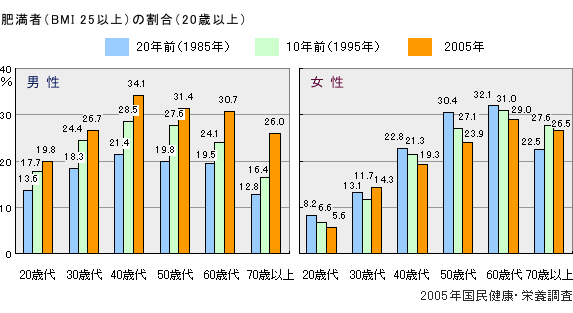
糖尿病の療養を続け、適正な栄養バランスを維持している患者は多くいる。そのための患者一人ひとりのさまざまな工夫の積み重ねがある。政府が進めている「食育」は「生涯にわたる健全な食生活と、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成を実現すること」ととらえられている。糖尿病患者の経験を食育に応用し、社会に教えられることも多いのではないだろうか。 ●詳しくは政府行政オンラインへ
生きる上での基本 「食育」の大切さ ●糖尿病の食事療法について下記で詳しく解説している
食事療法のコツ(1) [基礎](糖尿病セミナー)
[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所
食事療法の関連記事

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索