ニュース
2004年10月25日
お酒をよく飲む男性は糖尿病の発症率が高い
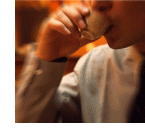
お酒を飲む頻度の高い人では1日に飲む量がビール大びん1本相当を越えると糖尿病を発症する比率が高くなることが、厚生労働省研究班が日本人のアルコール摂取と2型糖尿病の関連について調査した研究で分かった。
この傾向はBMI(肥満指数)22以下の男性で確かめられたもので、飲酒量が増えるにつれて糖尿病リスクも高くなるという。
この傾向はBMI(肥満指数)22以下の男性で確かめられたもので、飲酒量が増えるにつれて糖尿病リスクも高くなるという。
この研究は、厚生労働省研究班「多目的コホート研究(JPHC研究)」(主任研究者・津金昌一郎国立がんセンター予防研究部長)によるもの。対象となったのは岩手県、秋田県、長野県、沖縄県の4つの保健所管内の、糖尿病や心血管疾患などの疾患発症のない男性1万2,913人と女性1万5,980人の、計2万8,893人。調査開始時の年齢は40〜59歳だった。 調査では、開始から5年目と10年目に対象者に調査票を送付し、体重、身長、健康状態、喫煙習慣の有無、アルコール摂取状況、糖尿病や高血圧など医師による診断の有無、生活習慣について、自己申告で回答してもらっ
飲酒と2型糖尿病の発症について-概要-(JPHC研究)
[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所
糖尿病と肥満の関連記事
- 肥満でない人は糖尿病発症前に体重が減少する傾向にあることを発見
- 糖尿病と肥満症への対策を世界に呼びかけ 肥満は糖尿病に影響 治療は進歩 国際糖尿病連合
- 野菜や玄米の「植物ステロール」が糖尿病や肥満を改善 コレステロールを低下させインスリン抵抗性を軽減
- 高血圧対策では減塩が必要 魚介系ラーメンは血圧を上げない? こんな食事は食塩が多くなりやすい
- 野菜やお茶のポリフェノールが糖尿病や肥満のリスクを減少 メタボのリスクも大幅に低下
- 【夏はビールの飲みすぎにご注意】軽度の飲酒は糖尿病リスクを低下? ノンアルコール飲料を利用し飲酒量を減少
- 暑い夏の運動は涼しい夕方以降に ウォーキングが糖尿病や肥満を改善 週末1日だけの運動も効果は高い
- ワカメ・コンブ・海苔が糖尿病や肥満のリスクを減少 食物繊維が豊富で腸内細菌叢も改善 注目される「海の幸」
- 糖尿病と肥満のある人が体重を減らすとお得がいっぱい たとえ減量に失敗してもメリットが 食事日記をつければ成功率は2倍に
- 【運動が糖尿病リスクを減少】毎日のウォーキングが肥満やがんのリスクも低下 早歩きがおすすめ

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索