ニュース
2011年08月26日
魚をよく食べると糖尿病リスクが低下 インスリン抵抗性が改善
- キーワード
- 食事療法

「魚を多く食べる男性ほど、糖尿病の発症リスクは低下する」ことが、国立がん研究センター、国立国際医療研究センターなどが実施している多目的コホート研究(JPHC研究)であきらかになった。魚をよく食べる男性は、あまり食べない男性に比べ、糖尿病になる危険性が3割低くなるという。アジやイワシ、サンマなど脂が豊富な魚ほどリスクが低下することもわかった。
魚には良質な脂肪酸が豊富に含まれる
魚には、心筋梗塞や狭心症などの心血管疾患を予防する効果があるとされる良質な脂肪酸が豊富に含まれる。魚に含まれるのは、n-3系多価不飽和脂肪酸であるエイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)。n-3系脂肪酸をとることで、インスリン分泌やインスリン抵抗性も改善するという研究報告もあり、魚を食べることで糖尿病のリスクを下げる効果を期待できる。
調査は1990と93年に岩手、秋田、茨城、東京、新潟、長野、大阪、高知、長崎、沖縄の10都府県に住んでいた40〜75歳の男女5万2680人(男性2万2921人、女性2万9759人)が参加し行われた。参加者は調査時に糖尿病やがん、循環器疾患を発症していなかった。
研究開始から5年後に行なったアンケート調査の結果をもとに魚介類の摂取量により4つのグループに分類し、糖尿病発症との関連を調べた。
国立国際医療研究センター、国立がん研究センターなどの研究チームは、魚介類の摂取量により4つのグループに分類した。魚介類の摂取量(中央値)は、もっとも多いグループは男性 172g、女性 163g。もっとも少ないグループは男性 37g、女性 35gだった。
調理する前の魚の1切あたりの重量は、サバが40g、サケが90gくらいになる。1尾あたりではサンマが90g、アジが60g、イワシが40g程度(いずれも頭、骨、内臓をぬいた場合)。
5年間の追跡期間中に971人(男性572人、女性399人)が糖尿病を発症した。糖尿病の発症は、研究開始10年後に行ったアンケート調査で、期間内に糖尿病と診断されたことがある場合とした。
魚介類の摂取が多いほど糖尿病リスクが低下
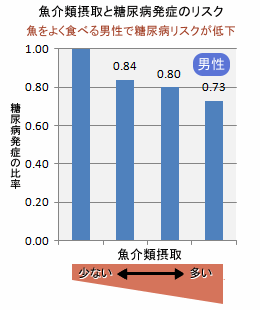
出典:多目的コホート研究「JPHC Study」
魚介類摂取と糖尿病との関連について 関連情報
白米をとりすぎると日本人女性で糖尿病発症のリスクが上昇(糖尿病NET)
腹部肥満がない日本人男性でも体重コントロールは有用(糖尿病NET)
大豆製品・イソフラボンの摂取で2型糖尿病のリスクが低下(糖尿病NET)
味の好みによる体重増加の違い 「甘い味」が好きな人は要注意?(糖尿病NET)
日常での「まめな運動」が長寿の鍵 死亡リスクが最大4割減 厚労省研究班(糖尿病NET)
[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所
食事療法の関連記事

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索