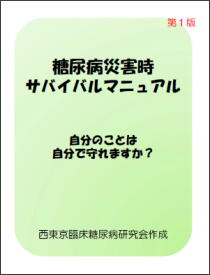ニュース
2013年06月19日
地震に備えて災害時マニュアルを制作 西東京臨床糖尿病研究会
- キーワード
NPO法人「西東京臨床糖尿病研究会」は、地震などの災害発生時に糖尿病患者と医療スタッフが適切に行動できるよう、優先して取り組むべきことを簡潔にまとめた災害時マニュアルを制作した。
直下地震は「いつ来てもおかしくない」 ふだんから準備をしておくことが重要
NPO法人「西東京臨床糖尿病研究会」(貴田岡正史理事長)は、震災など被災時の対応や、平常時の準備方法などを詳しく紹介した患者向け「糖尿病災害時サバイバルマニュアル」と、医療スタッフ向け「糖尿病災害医療マニュアル」の公開を開始した。
糖尿病患者自身と、医療者が使うことを想定。時間経過により変わる病態への対応を、「発災〜超急性期(72時間)」、「急性期(72時間〜1週間)」、「亜急性期(1週間〜1ヵ月)」に分けて解説している。
駿河湾から四国沖に延びる海溝「南海トラフ」沿いの地域で、マグニチュード8級の巨大地震が起こると警戒されている。東海から九州にかけて広い地域で、30年以内に起きる確率は60〜80%になる可能性がある。
東京でも23区から多摩地区にかけて液状化が起こり、津波も江東区で最大約2.5メートルに達するおそれがある。西東京地域は立川断層帯地震の直上にあり、多くの地域が激しい揺れに見舞われることが予想されている。
地震がいつ来てもおかしくないとふまえ、準備だけは整えておきたい。
NPO法人西東京臨床糖尿病研究会 糖尿病災害医療マニュアル
・ 医療者用 糖尿病災害医療マニュアル〜糖尿病を持つ人を支援する医療者のために〜・ 糖尿病患者用 糖尿病災害時サバイバルマニュアル〜自分のことは自分で守れますか〜
災害発生時「まず3日間は自力で生き延びよう」
西東京臨床糖尿病研究会は、東日本大震災発生後、糖尿病災害医療をテーマとしたプロジェクト会議やワークショップを展開した。災害時サバイバルマニュアルは、その成果をもとに作成したものだ。
患者向けの「糖尿病災害時サバイバルマニュアル」では、災害発生時に「まず3日間は自力で生き延びよう」を原則に、「災害に備えて、糖尿病治療に必要な物品や知識を準備しておきましょう」と呼びかけている。
飲料水、食料など一般的な避難用品の他、「お薬手帳」、「糖尿病連携手帳」、「自己管理(SMBG)ノート」、保険証(それらのコピーでもよい)などを準備する。さらに常用薬の予備、インスリン自己注射セット(インスリン製剤、注射器、注射針、消毒綿)、血糖自己測定器(穿刺器具、センサー、消毒綿)などを非常用持ち出し袋に入れ、自宅の分かりやすい場所に置いておくことが必要だ。
かかりつけ医や近くの医療機関と連絡がとれるように、連絡先や診察券の番号を書き込んでおくことも必須となる。
被災時に、自分は糖尿病患者で、どのような治療をどのように行っているかを他者に正確に伝えられるようにしておくことも重要だという。飲み薬やインスリン製剤の名前をはじめてとして、“薬を朝夕食後の2回内服している”、“1日4回自己注射を行っている”といった情報を、医療救護班の医師らに詳しく説明できるようにしておくことが心得だ。
NPO法人「西東京臨床糖尿病研究会」は、糖尿病災害対策委員会を中心に、糖尿病教室や講義やシンポジウムなどを通じて、患者向け「糖尿病災害医療マニュアル」と医療従事者向け「糖尿病災害時サバイバルマニュアル」の普及を目指している。
マニュアルは、下記ページでもダウンロードし閲覧できる。
・ 糖尿病患者用 糖尿病災害時サバイバルマニュアル〜自分のことは自分で守れますか〜
マニュアルは、下記ページでもダウンロードし閲覧できる。
NPO法人西東京臨床糖尿病研究会 糖尿病災害医療マニュアル
・ 医療者用 糖尿病災害医療マニュアル〜糖尿病を持つ人を支援する医療者のために〜・ 糖尿病患者用 糖尿病災害時サバイバルマニュアル〜自分のことは自分で守れますか〜
糖尿病災害時サバイバルマニュアル(患者向け)の概要
NPO法人 西東京臨床糖尿病研究会
地震予測に関する情報- 災害時基本行動三原則
- まず3日間は自力で生き延びよう
- 落ち着いてピンチの時こそ工夫で乗り切る!
- 見得も何もかなぐり捨てて、自分が糖尿病で助けが必要だと声を大にして言う
- 準備期 いまできること
- 自分の治療情報をまとめておこう
- 非常用持ち出し袋にいれるもの
- ふだんからしておくこと
- 超急性期 災害発生時〜3日目
- まずは生き延びよう
- 食事
- インスリン
- 怪我・ショックなどのシックデイ対策
- 低血糖の注意
- 受診が必須なとき
- 急性期 4日〜1週目
- 食事
- 生活での注意事項
- 亜急性期 1週間以上〜1ヵ月
- できるだけ普段の生活を取り戻す1ヵ月です。可能な限り受診しましょう。
- 食品・器具の取扱いについて
- 足のケア
- 口の中のケア
- 予防したいこと
- 衛生面
東海地震に関連する情報(気象庁)
地震の被害想定(東京都防災ホームページ)
[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索