ニュース
2006年10月26日
糖尿病患者は血圧も要チェック 進む治療薬の研究
- キーワード
糖尿病患者は血圧が高くなりやすい。糖尿病であると、糖尿病合併症を予防するために、血圧がそれほど高くない軽い高血圧でも積極的な治療が必要となる。高血圧症のより効果的な治療薬の開発が世界中で進められている。
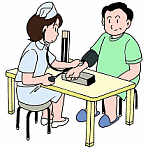 糖尿病と血圧について、 こちらで詳しく解説している。 |
糖尿病の人は血圧も要チェック
糖尿病患者は血圧が高くなりやすく、40〜60%が高血圧をあわせもつと考えられている。糖尿病と高血圧は共通点がある。どちらも症状のないまま進行することと、さまざまな合併症を引き起こすことだ。脳卒中や心筋梗塞などの病気は、糖尿病や高血圧が互いに影響しあい動脈硬化が進行した結果、発症することが多い。
英国で2型糖尿病患者を対象に1980年代に行われた臨床調査「UKPDS」では、食事療法や薬物療法による血糖コントロールが合併症を抑制し、さらに血圧をコントロールすることで、さらにその効果が高くなることが確かめられた。
糖尿病患者では、拡張期血圧値を10mmHg低下することで、糖尿病のすべての合併症を12%、最小血管障害を13%、心筋梗塞を11%低下させることができたという。
血圧の目標は130mmHg未満/80mmHg未満
日本の糖尿病の治療指標は、収縮期血圧(最高血圧)が130mmHg未満、拡張期血圧(最低血圧)が80mmHg未満(糖尿病性腎症がある人では125mmHg未満と75mmHg未満)。しかし、この目標まで血圧値を下げられないという患者は少なくない。
日本の高血圧患者の9割以上は、原因を特定することができない「本態性高血圧症」。塩分の多い食習慣、肥満、ホルモン分泌の異常、遺伝的素因など、さまざまな要因が考えられる。
治療として日常の生活習慣の改善がかかせない。塩分摂取の減少、肥満の解消、禁煙、効果的な運動などが有効とされる。血圧が十分に下がらないときは、薬による治療が始められる。より高い治療効果の得られる治療法や治療薬を開発するために、世界中で研究や開発が進められている。研究や開発が進む降圧薬
さきごろ福岡で開催された第21回国際高血圧学会で、高血圧症のリスクの高い日本人の患者約4,700人と、全国の600人以上の医師が参加した「CASE-J」と呼ばれる大規模臨床試験の結果が発表された降圧薬が発症予防に役立つという研究
第21回国際高血圧学会では、高齢者の高血圧治療についての大規模臨床試験「JATOS」の結果も発表された。JATOSは高齢の高血圧症患者の血圧値を下げる治療はどのように行えばいいのかを探った臨床試験で、日本高血圧学会の後援のもと日本臨床内科医会を中心に、全国1,000以上の医療機関で行われた。
塩野義製薬はこの試験で、長時間作用型の降圧薬(Ca拮抗薬)である「ランデル」(一般名:塩酸エホニジピン)による治療を2年間行い比較検討し、十分な治療効果を得られたと糖尿病性腎症に降圧薬 早期の治療が大切
万有製薬は4月に降圧薬「ニューロタン」(一般名:ロサルタンカリウム)が、糖尿病性腎症にも初めて使えるようになったと発表した。日本人も参加した大規模な国際共同試験による初めての承認例●詳しくはグラクソ・スミスクライン(株)のサイトへ(プレスリリース)
●詳しくは塩野義製薬(株)のサイトへ(プレスリリース/PDFファイル)
●詳しくは万有製薬(株)のサイトへ
関連情報 ・高血圧は積極的に治療する (糖尿病「ねほり はほり」)
・糖尿病と高血圧 (糖尿病セミナー)
・糖尿病による腎臓の病気 (糖尿病セミナー)
[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索