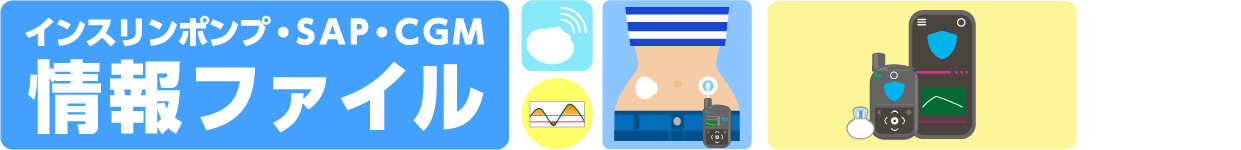第2回「インスリン療法としてのCSII導入の意義とコツ」
今回は、インスリン療法の名医として活躍される弘世貴久先生の登場です。特にインスリン療法の外来導入普及に尽力されたことでも有名です。「どうしよう?」と踏みとどまる患者さんに、どのようにアプローチしていくか。そのコツはインスリンポンプ(以下、CSII)導入でも参考になるのではないでしょうか。
1. インスリン療法導入の難しさと外来導入の推進

弘世 貴久 先生
(撮影:園田 昭彦)
留学から帰ってきたのが1995年。そして1997年までは大阪大学にいましたが、その後、西宮市立中央病院という一般病院へ行くことになりました。それまでは大学の研究、特に基礎的な研究しか興味がなかったのですが、糖尿病を診られる人が誰もいないところに僕1人放り込まれ、孤軍奮闘しているうちに糖尿病診療が面白くなり好きになりました。
この病院に来てすぐは、外来患者にHbA1c10%以上の人がぞろぞろいて、インスリン導入されている人もシリンジでNの1回打ちをしている人が多かった。当時、混合型も使用可、しかもペン型も発売されていたのにです。これはあかん!てね。まずは、入院できる人は入院させてインスリン導入をやり直しました。ただ、入院できない一群がやっぱり残ってしまう。
当時、インスリン導入は入院して行うのが普通だったんです。学会でも導入は入院でやるべき、1〜2回注射で、という発表が一般的で、働いている患者さんを多く受け持っていた僕としては現実的ではないなと思っていました。まだその頃は「仕事を休めないから入院できません」と断ると、「じゃあ、あなた死にますよ」とか言っていた時代です。
サラリーマンの方が2週間休むのは簡単ではないですからね。多くの患者さんが困っているのを目の当たりにして、やっぱり外来でできるようにならないとだめだなと思いました。とはいえ、あの時代は誰もやっていなかったので、外来導入の方法を自分で確立していくしかなかったのです。
そして、インスリン導入したいけど入院できない一群の患者さんに対して、外来導入を試行錯誤しているうちに、だんだんできるようになりました。看護師さんも最初は戸惑っていましたが、慣れてくると問題なくこなせるようになり、「導入外来」を作ったら、外の病院からも患者さんがわんさか集まりました。みんな困っていたんですね。それで、ノウハウを公開して標準化できないかと本をだしたんです(『これなら簡単 今すぐできる外来インスリン導入』メディカルレビュー社刊)。
本を出した威力はすごいものでした。学会や講演に行くと「あの本はよかったです!」、「うちでも外来導入をはじめました」と全国から反響をいただきまして、本当に嬉しかったですね。
外来導入では、最初は患者さんに週1回通院してもらい、そのうち2週間、1カ月と間隔を空けていきます。少しずつ慣れていくやりかたです。要するに、慌てる必要はないということ。様子を見ながらゆっくり半年くらいかけてやるくらいのイメージですね。入院だと「様子を見ながら」とか言っていられませんから。慌ててコントロールつけてええカッコしようとするから低血糖になるんですよ。初期は1日3単位でも2単位でも、もっと言えば効かなくてもいいんです。その代わり、入院しているときみたいに薬を全部やめずに残していれば悪化することはない。そんな話を本に盛り込みました。
患者さんにとってチャンスは広がりましたね。それだけでなく、患者さんの負荷をいかに減らすか、インスリン療法は怖くないとどうしたら納得してもらえるか、どう説明しようか、私たちはずっと考えてきました。
逆に医者側、医療従事者側のほうがインスリン療法を怖がっているような気がします。低血糖が怖い、面倒くさい、わからない、難しい、、と。一般内科では、糖尿病は診るけどインスリン療法はやらないというところは多くあります。
そう、医者がやる気にならなきゃ無理です。糖尿病診療は、悪く言えばいい加減にやっても済むんです。HbA1c8%でも、今すぐどうにかなるわけではありません。心配しているのは将来の合併症のことだから、極端に言えば「がんばってね!」と言ってるだけでも外来は成り立ちます。ですから、医療従事者側のやる気、熱意がないと患者さんのコントロールは良くなりません。
うるさく言われると患者さんは嫌だろうけど、熱心な医者にかかれているのは幸せなことなんです。師匠の河盛隆造先生(順天堂大学大学院教授)は"糖尿病は放置病だ"と表現していますけれど、本当にそうなのです。患者さんも医療従事者も、放置してはだめ。
例えば、大学病院では、インスリン療法で大血管障害を抑え、30年後の合併症予防をどうするかといったテーマをもって研究しています。一方、一般の診療現場では今、どうすれば血糖値が下がるか、HbA1cがよくなるか、それが課題でありすべて。毎日の生活で血糖コントロールができていない患者さんが目の前にいれば、そこに応えていかなくてはなりません。どちらのレジメンが将来の合併症抑制にEBMとしていいのかというのではなく、目の前の患者さんにどちらの治療がよいのか、答えが必要なんです。
2016年07月 公開

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索