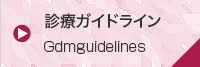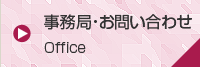会報 2005 April Vol.7 No.1
【巻頭言】
日本人の食事摂取基準(2005年版)と妊婦の糖尿病管理
立川 倶子
社団法人鹿児島県栄養士会会長
今般、平成17年度から21年度までの5年間に使用する「日本人の食事摂取基準(2005年版)」が発表された。生活習慣病の一次予防の観点から当面の目標とすべき摂取量として「目標量」が新しく設定されたことなどを始めとして、エネルギーや各栄養素について科学的根拠に基づく新しい知見が加えられている。
妊婦・授乳婦についても非妊娠時、非授乳時の食事摂取基準を年齢階級別に算定した上で、妊婦、授乳婦ではそれに付加すべき量として設定されている。
とくに今回の改定では、エネルギー量について妊娠期間を細分化し、初期(16週未満)、中期(16週〜28週未満)、末期(28週以降)に3分割し、初期50Kcal/日、中期250Kcal/日、末期500Kcal/日を付加量としている。前回が妊娠期間を一律に350Kcal/日の付加量としたことと大きく異なるところである。たんぱく質についても、従来、妊娠中のたんぱく質付加量は要因加算法で算定されていたが、今回は、妊娠中のたんぱく質蓄積量を体カリウム増加量より間接的に算定している。
また、もっとも大きな変化は、カルシウムの食事摂取基準である。妊娠中におよそ30gのカルシウムが母体と胎児に蓄積し、その蓄積の大半は妊娠末期に起こる。そのため、妊娠中はカルシウム付加量が必要と考えられていた。しかし、妊娠中は活性型ビタミンDやエストロゲン等が上昇するので、腸管からのカルシウム吸収率は著しく上昇する。日本人を対象とした出納試験でも、カルシウム吸収率は非妊娠時23±8%に対し、妊娠末期には見かけ上42±19%に上昇していた。さらに、エストロゲンが高値を示すにもかかわらず、母体の骨量は生理的に減少する。その結果、カルシウムは胎児側へ蓄積されると同時に、尿中への排泄量も著しく増加する。そのため、若年妊娠の場合を含め、年齢階級別に示された目安量を摂取している妊婦では、付加量は必要がない。ただし妊娠中毒症などの胎盤機能の低下がある場合は、カルシウム吸収率は増加しないので、カルシウム付加量は相当量が必要である、と解説されている。
さらに、授乳婦についても従来、母乳中へ大量のカルシウムが移行するので、授乳婦には付加が必要と考えられてきた。しかし、授乳中は腸管でのカルシウム吸収率は非妊娠期に比べて軽度に増加するにすぎず、尿中カルシウム排泄量は減少して、母体の骨量は減少する。これは、母乳中のカルシウムが主に母体の骨カルシウムに由来していることを示している。そのため、たとえカルシウムを多く摂取しても母体の骨量減少は阻止できない。ところが、授乳終了後の約6ヶ月間で、減少した骨量は、ほぼ妊娠前の状態にまで急速に回復する。そのため、年齢階級別に示された目安量を摂取している授乳婦では、付加は必要としない。
前回は、妊娠期300?/日、授乳期500?/日の付加量とあり、今回は付加量0と設定された。解説を読めば理解できるが、あくまでも非妊娠時のカルシウム摂取量が十分であることがその前提となっている。しかし、日本人のカルシウム摂取量の水準は低く、とくに妊娠可能な年齢である18〜49歳にかけての摂取量は少ない。したがって、妊娠・授乳という機会にカルシウム摂取量を増やすよう心掛けることも大切である。
今回の食事摂取基準は、あくまでも健康人を対象としたものであるが、糖尿病管理にも十分参考になる。これらのデータをいかに糖尿病妊婦の栄養管理に活用するかも重要な課題である。本学会での貴重なデータの蓄積に期待したい。
理事長の大森安恵先生のご推薦により、第16回学術集会から理事の末席に加えていただき、第20回学術集会まで務めさせていただきました。この度、理事を退任させていただきますが、本学会の諸先生方へ深く感謝申し上げますとともに、日本糖尿病・妊娠学会のますますのご発展を心からお祈り申し上げます。
大森賞を受賞して
秋吉 澄子
長崎大学医学部・歯学部附属病院生活習慣病予防診療部
この度は、第20回日本糖尿病・妊娠学会におきまして、栄誉ある大森賞をいただき誠にありがとうございました。今回受賞いたしました「妊娠糖尿病患者の分娩後における糖尿病発症予知因子の検討」に関する研究は多くの先生方、看護師、栄養士の皆様方の長年にわたるご尽力の賜物です。ここに深く感謝申し上げます。
妊娠糖尿病患者は将来、高頻度に糖尿病を発症することが知られています。しかし、産褥期には耐糖能が著しく改善するため、耐糖能がいったん正常化する症例も多く、分娩後の内科的フォローアップは不十分になりやすいのが現状です。そこで本院では、分娩後のフォローアップシステムを設け、産褥期に境界型や正常型を示した症例に対しても、定期的な内科診療、生活指導、栄養指導などを行っております。このようなフォローアップを行っていく上で、糖尿病発症のハイリスク者を同定し、できるだけ早期に発症予防策を講じることは大切なことです。
分娩後の糖尿病発症の危険因子として、これまでに我々は、妊娠前BMI≧24、妊娠糖尿病診断時HbA1C≧6.2、FPG≧100が重要であることを報告してきました。今回の発表では、これらの危険因子のうち、FPGの関与がもっとも強いことが明らかになりました。今後は、このような糖尿病発症の危険因子を持つ症例において、個々に応じたオーダーメイド的な予防法の模索が必要であると考えています。
これからも諸先生方のご期待に沿えるよう研究を進めてまいりたいと思います。ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。
洲脇 尚子
岡山大学大学院医歯学総合研究科産科・婦人科学
この度は、第20回日本糖尿病・妊娠学会にて栄えある大森賞を授与いただきまして、大変光栄に存じます。理事長の大森安恵先生、中林正雄先生を始め、選考委員の諸先生方には厚く御礼申し上げます。
また、実際の研究に際して、直接ご指導賜りました平松祐司教授ならびに増山寿先生、さらに日々ご支援をいただいている教室の諸先生方に深謝申し上げます。
本研究では、現在、生活習慣病の中でもとくに2型糖尿病の病態解明において注目されている、核内受容体型転写因子Peroxisome Proliferator-Activated Receptorγ(PPARγ)の糖尿病合併妊娠、とくに胎盤形成における役割について、糖尿病マウスおよびヒト絨毛細胞を用いて検討を行いました。高糖濃度環境下で認められるさまざまな細胞レベルの異常は、PPARγのリガンドを投与することにより改善を認め、高度な高血糖状態においてIUGRの原因となる胎盤機能不全の治療につながる可能性が示唆されました。
この度の大森賞受賞を励みとし、今後も研究・臨床ともに精進してまいりたいと思います。今後ともご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。
診察室だより 北から南から
自由ヶ丘横山内科クリニック
横山 宏樹(院長)
帯広市は、十勝地方35万人の中心にある町です。当医院は平成12年10月に開業して4年が経ちました。
私は、大森安恵教授のもと東京女子医科大学糖尿病センターにて14年間学び、ヤング糖尿病と糖尿病性腎症の臨床と研究に携わってきました。糖尿病は地域医療を根幹としていることを痛切に感じ、在学中にたくさんの臨床例から経験させていただいたことを地域で活かし、臨床と研究をライフワークにしたいと考え、十勝へ来たのが5年前でした。この地は、住環境としては最高の自然に恵まれています。しかし、大学病院がなく、医療連携の意識もあまり高くありません。開業がこの地元に受け入れられる最善の形であると認識して、思い切って開業しましたが、開業時の糖尿病患者はわずか月30人で苦渋しました。
実は2年前に、十勝産婦人科医会から、"妊娠と糖尿病"に関しレクチャーを依頼され、その準備もあり、妊婦の血圧管理やアルブミン尿など含め再度必死に勉強しました。その折は、大森教授と鹿児島の加治屋昌子先生に大変お世話になりました。その会で、妊娠前教育、妊娠中の血糖コントロールの重要性、ヤング2型糖尿病の重症合併症の怖さを話したところ、以降、しばしば産婦人科から患者紹介をいただいています。現在は、約800名の糖尿病患者さんが受診される中、年15〜20例の妊娠糖尿病を含む糖尿病妊婦をみています。さらに産後に耐糖能が正常化した例の耐糖能の追跡も始めています。
十勝の特徴として、若い女性でも肥満が多いことが挙げられます。昨年の第20回日本糖尿病・妊娠学会において、初めて当医院から発表させていただきましたが、その自験例でも、24例中5例が肥満でした。1型糖尿病は、妊娠前教育を行った上で妊娠・出産に臨んでいますが、1型糖尿病以外は、妊娠後に産婦人科から紹介される例がほとんどであるのが実情です。しかし、産婦人科の先生方が糖尿病妊婦管理に内科との連携の必要性を認めて下さるようになったことに励まされています。そして"糖尿病と妊娠"の臨床の深さに直面し、改めて地域医療の一端を担う責任を感じる毎日です。
日本の小児ヤング糖尿病治療と全国規模の集会が果たした役割
内潟 安子
東京女子医科大学糖尿病センター教授/小児ヤング外来チーフ
日本における小児糖尿病(今日の1型糖尿病ないしインスリン治療の必要なやせ型2型糖尿病のことを指す)の治療は、新美仁男先生が1992年に書かれたものを読むと、昭和30年代までの報告は100例あまりだったとのこと。昭和45年に、初めて全国規模での調査が三木、丸山らで行われ、14歳未満発症患者は619人と報告された。このような状況下で最初のサマーキャンプが開催されたのは昭和38年東京で、6年後に福岡、熊本、その後全国に広がっていった。「インスリンが絶対に必要である子どもの糖尿病」がどうやっても十分な理解を得ることのできない時代にあっては、サマーキャンプは唯一の治療と教育の場となった。HbA1CもSMBGもまだ存在しない、インスリン自己注射も健保適応(1981年)になっていない頃である。その一方で、1974年(昭和49年)に18歳未満小児糖尿病が小児慢性特定疾患事業の中に包括され、治療費が無料となったことは特記すべきことであった。
1979年(昭和54年)に小児若年糖尿病全国ジャンボリー(河野泰子先生のお世話で)が鹿児島から始まった。翌年、東京で第1回ヤングDMトップセミナー(池田義雄先生のお世話で)が開催された。以後、毎年交互に開催されて、4年前に全国ヤングDMカンファランスにとって変わるまで、日本の小児糖尿病患者の仲間作りとサマーキャンプ指導者の育成に大きな役割を果たしてきた。このような努力の結果、小児期発症糖尿病を持つ女性が成人したのち安心して妊娠、出産できるようになった。
小児の1型糖尿病に対して、紆余曲折はあったが、多くの方々の努力に支えられて今日に至っている。昨今は、小児2型糖尿病に対しても、同様の方策が必要になってきたと痛感している次第である。