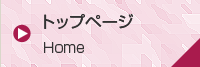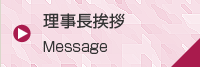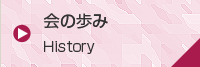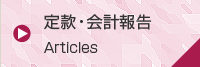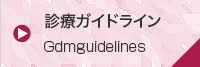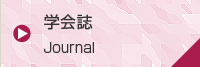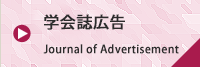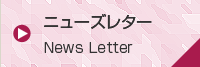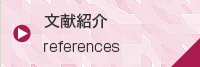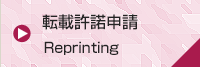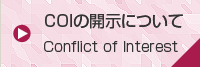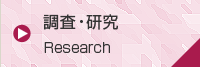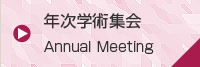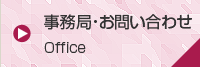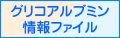日本糖尿病・妊娠学会の学会員になって皆と語り合いませんか?
2025年01月16日
日本糖尿病・妊娠学会教育担当常務理事
守屋達美
2023年の第39回日本糖尿病・妊娠学会(以下本学会)年次学術集会で、「学会に行こう、症例報告を出そう、研究をしよう、論文を書こう、そして若手奨励賞・大森賞を目指そう」というお話をさせていただきました。近年、耐糖能異常を合併する妊婦さんは増加しており、本学会はその診断と治療の原則だけではなく、治療の具体的なノウハウやケアに関して様々な意見交換をしています。したがって、実際に耐糖能異常を合併する妊婦さんを現場で対応している方々、これから対応しようと考えている方々などの皆様の参加や意見交換が非常に重要であると考えています。本稿は、上記の年次集会で発表した時の抄録および発表内容を修正加筆したものです。
ぜひ、最後までお読みいただき、そして本学会の学会員になっていただき、会場で一緒に意見交換をしませんか?
目 次
- はじめに
- なので、まず学会に出かけてみませんか?―日々の臨床業務から学会参加へ
- そして、質問をしよう
- まずは症例報告から始めてみましょう
- 少し慣れたら研究をしてみましょうか
- 論文を書いてみよう
- 自施設に相談できる上位者がいない場合
- テーマどうやって見つける?
- 一方、指導的立場にいる方(医師とは限りません)へのお願いです
- 目指せ!若手奨励賞・そして大森賞
- 少しずつハードルを超えよう
- 繰り返しますねーまずは日々の臨床業務から学会参加へ
- おわりに
はじめに
日々の臨床業務の中で、「あっ、この症例にはもっとこうすればよかったかも」と思うことがあります。一方、「この療養指導や治療でよかったんだ」と思うこともあります。私たちは、その経験から必ず何かを学んでいます。それらの「学び」をなるべくたくさんの人たちと共有し、自分の経験や知識をブラッシュアップすることは次の診療につながります。これは、とても重要なことです。その一つの方策は学会参加だと考えています。
なので、まず学会に出かけてみませんか?―日々の臨床業務から学会参加へ
自分の経験例と似たような経験をした人はいないかな?と思うことがあるでしょう。
ぜひ、他施設の方々の意見を聞いてみましょう。施設ごとに診療システム・考え方・方策・治療手順などが違うことがあります。世の中には様々な同業者がいて、様々な考え方があります。学会に参加すると、他施設の方々と交流が生じ、自分の視点・世界が広がります。対面の学会に行っても「ただ聞いているだけ」であれば、WEBでも良いかもしれません。しかし、学会をWEBで聴くのと実際の場で聴くのとでは、印象が全然違うと思います。色々な人と知り合いになりたい、それなりにディスカッションしたい、理解を深めたい、と思う方は、会場に行った方がはるかに実りが多いと思います。
私事になります。今となっては古い言葉となった「ペットボトル症候群」の症例発表を糖尿病学会の関東甲信越地方会で初めて聞きました(1994年頃です)。その演題を聴き、仲間、先輩と「こういう人、僕らのところにも何人かいるよね」と話しました。じゃあ見直してまとめてみようか、ということになりました。これは、臨場感あふれる学会会場だから気づいた部分は大いにあります。そして、先輩や同僚と一緒に参加したからこそ味わえた感覚です。その後、若手医師が20例ほどをまとめて後の糖尿病学会年次学術集会で発表することができたのを覚えています。
そして、質問をしよう
学会に参加したら、頑張って質問をしてみましょう。
最初は、質問するのは気後れします。私も若い頃は本当に質問しづらかったです。でも、3、4回も質問すれば慣れてきます。同時に自分の知識・経験の広がりを実感するでしょう。一般演題の 1セッションは1時間であることが多く、演題が5、6題あります。そして、1、2人の座長が担当していて、その座長は有名な人(憧れの人?)が行なっていることが多いです。私自身は、その憧れの人に自分のこと覚えてもらいたいなと思い、座長一人に対して最低一つの質問を心がけました。もちろん、質問するためには、必ず事前にそのセッションの抄録集を読むことになります。
まずは症例報告から始めてみましょう
症例報告は、倫理申請の必要はありません。私は、その昔の上級者からから「症例報告は非常に重要だ。全世界でその1例しかいないのだから。」と言われ、何度か本学会にも症例報告をしてきました。ぜひトライしてみてください。そして、学会発表をしたら本学会雑誌の「糖尿病と妊娠」にその症例報告を論文として投稿してみましょう。学会発表で使用したスライドの一部は症例報告の原稿に転用できますよ。
少し慣れたら研究をしてみましょうか
症例報告ができたら、次に何例かをまとめてみましょう。10例、20例と蓄積していくと1例だけではわからなかった様々なことに気がつきます。疑問点も生まれ、さらなる研究の着想に至ります。日々の診療の中で感じる疑問点・何を明らかにしたいのかを明確にすることにもつながります。
論文を書いてみよう
ある程度纏まった検討をしてくると次に控えているのが論文投稿です。
まず、投稿規定を熟読しましょう。そして、先行研究をサーチしましょう。他の人が書いた論文をよく読みましょう。「糖尿病と妊娠」に掲載された論文を過去5年分くらいみて、どのような研究がなされているかを調べると、そこから新たなアイディアが生まれてくると思います。倫理申請のハードルは低くはないですが、その際に作成する研究計画書はそのまま論文に応用することができます。倫理申請の研究計画書ができれば論文の半分はできたと思います。自施設に倫理委員会がない場合でも、周囲を探せば必ずそれを有している施設はあります。大抵は外部からの申請も受けているはずです。それを探してみましょう。その意味でも外部に知り合いがいると良いのですよ。
論文が掲載されれば、この広い世界の中できっと誰かが読みます。お問い合わせをいただくこともあります。論文が出来上がったときの喜びはとても大きいです。
自施設に相談できる上位者がいない場合
研究内容をディスカッションできる相手や指導者を見つけることは大切です。師匠を得ることは容易ではないこともありますが、同じ分野の診療を一緒に行っている自施設の他部署の人や学会懇親の場などで他施設の方と積極的に交流を図りましょう。このことからも学会に出かけて行って仲間を見つけることは非常に重要だと思います。
テーマどうやって見つける?
一見、大きな問題に見えますが、日々の臨床現場でいかにリサーチクエスチョンを持つ姿勢があるかないかにかかっていると思います。
ぜひ、リサーチクエスチョンを持ちましょう。それには、日々の臨床業務の中で少しでも疑問を持つことです。
■単純に知りたいと思うことはないでしょうか。
■この1年でどのような患者さんと接したのか(本学会に関連することなら何人の耐糖能異常合併妊婦とお会いしたのか)思い出してみましょう。2、3例しかいなくても構わないです。でも見直してみるとそこに「反省」そして「学び」があると思います。
■一度発表(症例報告で構わないです)を経験するとよりリサーチクエスチョンを持ちやすくなります。
一方、指導的立場にいる方(医師とは限りません)へのお願いです
ぜひ、仲間を連れて学会に参加することを考えてください。
■自分だけが参加するのではなく。
■一緒に参加しよう、一緒に演題を出そう、というノリで。
■仲間(メディカルスタッフや後輩医師)の微細なやる気のサインを見逃さないでください。
■さらには仲間が書いた抄録・論文をよくみてあげてください(迅速に)。
この「糖代謝異常合併妊娠」の診療は、様々な職種が関与するチームで行っていることがほとんどではないでしょうか。したがって、日常診療業務をチームで行うだけではなく、様々な研究関連活動もチームで行うことをお勧めします。
目指せ!若手奨励賞・そして大森賞
少しadvanced courseになりますが、研究・論文を積み重ね、より高みを目指すことも大切です。素晴らしい論文には、本学会から若手奨励賞や大森賞が授与されます。年齢などの制約がありますので、まずは規定をご参照ください。そして少しでも質の高い研究を目指してください。そうしていれば、賞はあなたの後からついてきます。
まずは若手奨励賞かな。
少しずつハードルを超えよう
今回申し上げてきたことには、いくつかのハードルがあります。
・学会に参加する
・学会員になる
・症例報告を出す
・まとめた発表を出す
・論文を書いてみる
上記のように、それぞれのレベルでハードルはたくさんあるかもしれません。でも、一つ超えると必ず自信がつきます。新しい世界が広がります。一つずつ良いから越えていきましょう。
繰り返しますねーまずは日々の臨床業務から学会参加へ
自分の経験例と似たような経験をした人はいないかな?と思うことがあるでしょう。
ぜひ、他施設の方々の意見を聞いてみましょう。施設ごとに診療システム・考え方・方策・治療手順などが違うことがあります。世の中様々な同業者がいて、様々な考え方があります。
学会に参加すると、他施設の方々と交流が生じ、自分の視点・世界が広がります。 そして臨床研究は非常に重要ですー日々の臨床業務の解決策の大部分は臨床研究の中にあります。自分自身の経験例をまとめてみようというお話をしましたが、その「まとめ」の中にも臨床業務の解決策があるはずです。
おわりに
「糖尿病と妊娠」の分野は現在発展途上で、医療者の関心は明らかに高まっています。
したがって、実際に糖代謝異常合併妊婦の診療・ケアに当たっている現場の皆様の知識・経験の発信は非常に貴重です。ぜひ、年次集会の場でたくさんの方々(同職種でも異職種でも)と交流し、日頃気になっていることを語り合いましょう。
皆様のご参加をお待ちしています。