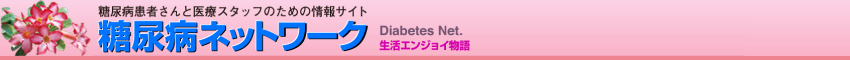第6回は、関東労災病院の新良啓子さんを訪ねました。糖尿病療養指導士(CDE)や糖尿病看護認定看護師でもある新良さんは、糖尿病療養指導のプロフェッショナル。栄養士さんによる間食指導とは違った、糖尿病療養指導の側面から、間食指導について語っていただきました。
糖尿病療養指導の中での間食指導について
糖尿病患者さんの間食を、どうお考えですか?

糖尿病療養指導士としての役割について
新良: 糖尿病療養指導の看護師としては、患者さんの治療の状態を見ながら、必要に応じて生活習慣指導などを行います。医師から要請があって指導室でお話を伺うという方ももちろんいらっしゃいますが、カルテを見て気になる方は私の方から声をかけて、待ち時間の中で指導室に呼んでお話することもあります。管理栄養士さんによる食事指導の場合は有料(点数もつく)ですので、医師の指示によってやるかどうかを決めます。あと、血糖コントロールを改善するために、食事に関して専門的なアドバイスや管理が必要な患者さんがいらっしゃった時、“栄養指導を受けたいな”“もっと詳しく聞きたい”と思えるように仕向けることも、大切な役割と考えています。
ドクターと栄養士さんの間に入ってどんな生活をしているかをよく聞くのですが、「菓子パンを食べている」と仰った時、「どんな菓子パン?」と聞くと“やきそばパン”と言う方もいます。食事パンも菓子パンと思っている人もいるのです。そして、「いつ、どんな時にそれを食べているか」、具体的な部分を聞き出さないと実態がつかめません。あと、最近こだわりの食べ物、マイブームなど、患者さんの嗜好を会話の中で聞き出すことも大切で、そこから会話が盛り上がり、食生活の実態を掴めるだけでなく、関係性も良くなります。
「24時間軸」から患者さんの生活を把握する
新良: 私の面談ではいつも、患者さんが24時間をどのように過ごしているかを、平日・休日パターンで聞きとりを行います。時間軸を手描きで書いて、「この時間は、何をしていますか?」と、図を見せて1つ1つ書き込みながら、24時間軸を患者さんと完成させていきます。すると、食事の時間、仕事の状況、家族との過ごし方など、生活パターンが見えてくるので、さらに踏み込んだ話の中から、問題点を引き出すことにつながったりもします。聞き取りを行う時に、工夫していることはありますか?
新良: 患者さんへ質問する時の言葉遣いには、とても気を遣います。「なぜ?」「なんで?」という言葉で患者さんに詰め寄ると、悪いことをした理由を聞かれているように誤解されることもあるので、「その理由をちょっと教えてくれませんか?」、「ちょっと、立ち入ったことを伺いますが」、「仰りたくなければ仰らなくてもよいですけど」など、枕詞を使ったたり。言葉を置き換えながら、こちらがなぜ聞きたいかを明らかにして質問します。最初あまり何もしゃべらないような方は逆に、懐に入るといろんなことを考えていて、そういう方たちこそ自分で何とかしようと思っていたるすることが多いんです。でも、病気をよくするために来ているという目的がありますし、患者さんも、そのために必要な情報であればと、たいていは答えていただけます。聞き取りについては、やっぱりトレーニングはしましたよ。置き換え言葉を使うと、すう〜っと患者さんから話が出てくるので、聞き方は大切なんだなと実感しています。
<聞き取り例>
- 「こんな甘い物食べたらだめじゃないですか」→「(一緒に食べ物を書き出し)甘いものが多くて心配です。今回、甘いものをたくさん食べた理由をお聞かせくださいませんか?」
心配を示し、怒っているのではなく関心を持っていることが伝わるようにする。「今回」と限定したことで、患者さんが自分を振り返る範囲を狭め、振り返りしやすいようにする。 - 「なんで夜中にスナック菓子を食べちゃったの?」→「食べたあとの感想はどうですか?」「夜中に食べようと思ったのはなぜですか?」
どちらも患者さんの考えを引き出すように気をつける。無意識にしていることを意識化していただくためです。 - 「○○しましょうね(上から目線)」→「これから、お菓子たちとどんなふうにつきあっていきましょうか。今、考えていることをお話してください」
人は、自分で決めたことしか行動しない。「今」をあえて言うのは、今の考えで良いから。訂正はいくらでもできる。方法は無限で自由であることをわかってほしいと思うからです。
指導の中で、間食の話題が出てきたりしますか?
新良: 実は食べているのよ、という話は、SMBGの結果を一緒に見ながらだとよく出てきます。「別に、、」という頑なな態度の方は、過去に医療者からプレッシャーを受けたことのある方だと思うので、そういうことを言いやすい環境を作ってあげることが大切です。“こんなことを言うと怒られる”など、今までいろんな仕打ちを受けてトラウマを持ってる方もいらっしゃるので、言いやすい雰囲気を作ったり、そういう話題に持って行けるよう、こちらから上手に聞き出したりする必要があります。
また、間食の話を聞いた際には「美味しかったですか?」と聞いたりします。まずは共感。でも必ず患者さんが「血糖値が上がるってわかってるんですけどね」などと続けます。「実はこんなの食べちゃったのよ〜」って気軽に正直に言える関係作りをするのは大切です。“正直に言える患者さん”は、「これを食べたらこうなって、これだとこうだった」とか、反省半分、自己分析をしていたりします。SMBGをしている人は特に。この反省や自己分析の繰り返しは重要だと思っています。
本当は、先ずはドクターが「間食禁止は無理よね」と認めてくださると、医療スタッフはやりやすいかもしれません。診察時に、「ナースが食べていいとを言ったから食べた」などと、ドクターに言い訳されても困りますからね(笑)。
間食を賢くチョイスするための情報は?
新良: ネットを見られる方は、「間食指導の情報ファイル」を実際本当にお勧めしています。あと、神奈川県のこの辺りでは、平尾先生達が作られた「彩の会」が作った80kcal和菓子を取り扱っている所が多くて、そういうお店がありますよとお勧めしたりします。
指導を行った患者さんの例をご紹介ください。
症例1) 夜は間食、夜中に夕食の生活で・・
新良: 奥さんがインスリン療法中の糖尿病患者さんで、旦那さんはコンビニ経営。下が店舗で上が住居というような環境だそうです。治療歴は20年近く。この頃、インスリン療法を行っていてもHbA1cは9%切る位で、コントロールがずっとよくないのと、待合室でぼんやり考え事をしている姿を見て、ちょっと事情を聞いてみようと思い、指導室でお話を伺いました。コンビニは、ご主人が主に経営していて、手伝いはバイトの学生さん。でも春先で学生さんの入れ替えなどで人手が足りなくなると、奥さんも手伝っているとのことでした。自営業をしていると、GWや夏休みでバイトがいなくなったり、不況のあおりを受けたり、いろいろと悩みがあるんですよね。ですから、彼女にも時期によって負荷が大きかったようです。そんな話が、少しずつぽろぽろと出てきました。でも、まだ表情がすっきりしない。 次回の受診日にまた面談を行いました。すると、今までに話題がなかったお姑さんの話が出てきたんです。話をしている中でそれが問題の核になっているのではと思いました。3回目の会話でやっと、「実は、姑が・・」という話をするようになって、表情が変わりました。話によると、それまで、ご主人の仕事が終わるまで、夕食を23時過ぎまで待っていたそうです。でも待っているとお腹がすいてしまうので、間食していたんですね。そして夜中にもご主人に付き合って一緒に夕食を食べていた。 そこまで掘り出さないとわからない。SMBGの記録でも夕食前と書いてあっても、その人によって何時になるかは異なります。この方のように23時過ぎという人もいらっしゃるわけです。子供がいなくて、お姑さんが年をとったので田舎へ帰ってこないかと言われるも、ご主人は頑張ってるからそんなことは言い出せない。もともと保育士さんだったそうで、子供ができなかった負い目もあったのかもしれません。そんな環境だったので病気の治療など、あまり堂々とやりにくかったんですね。 でも、話をしたらすっきりしたようで、私、やっぱり治療をがんばります、と。そんなきっかけでやる気が出るようになって。どんな状態か食事の状況を栄養士さんにみてもらいましょうか、と誘い栄養相談を受けて頂きました。その後、大きな改善点としては、ご主人に「血糖コントロールの状態が悪い。食事の時間が遅いのはよくないから、先に食べるね」と言えたこと。今まで、頑張ってるご主人に言えなかったんです。今までは、夕食を待って一緒に食べることがご主人へのサポートと思っていた。でも、こういう状態を続けていくことで、いずれ合併症など大きな問題が出てきて、もっとご主人に迷惑がかかるかもしれない、と考えることができるようになった。自分の体をよくして、旦那さんをサポートしていこうという気になったようです。結果的に夕食の時間を変えたことで、1日の栄養摂取量も変わり、半年くらいかけて現在は7%代に安定していきました。間食内容は、お菓子だけでなくコンビニの賞味期限切れのものを毎日食べていたようです。
症例2) 電子レンジを置く場所からアドバイス・・
新良: 循環器科からまわってきた30代後半・肥満のある独身男性患者さん(100kg越え)で、職業はSEをやっておられる方。気の毒な位、生活サイクルがめちゃくちゃで、長時間座って作業しているそうです。おとなしくてあまり人とのコミュニケーションが上手な方ではありませんでした。IGTレベルでしたが、検診でひっかかってきて、HbA1cは6.7%。血圧の薬は飲んでいたようです。 1カ月だけ朝晩体重はかって、食べたものを書いてメールで送ってくれますか?と依頼しました。パソコンは得意なので、3食の記録をきちんとつけてきてくれました。それを見てみると、その方は1日中食べ続けているような習慣を送っていることがわかりました。食生活を変えなくちゃいけないね、という話に当然なるのですが、独身男性は生活管理は難しいですよね。電子レンジも家にない世界です。ご自身曰く、部屋はゴミ屋敷で、レンジを置く場所がないと仰られて。その時は間取りを書いて、どこに何を置いてるかを聞き、ならこれをこう片付けたら?と、まずはレンジの場所を確保することから始めました。 そんな経緯の中で、レコーディングダイエットで80kg前半まで落ちたんです。でも、最終的には病院へ来なくなってしまいました。考えてみると、彼は私に言われたからやっただけで、自分からやりたくてやっていたわけではない、ということだったのではないかと思うんです。そして、彼にとっては、やせたことのメリットも感じられなかった。ズボンが緩くなったといっても嬉しそうでもなかったですし。。そんな失敗例だったのですが、今となっては、どんなふうにあのとき考えていたのかなと気持ちを聞いてみたいですね。 こういう例を経験すると、やはり患者さん自身、その先のことを考えているかどうかが、療養上のコンプライアンスとして重要だと思うんです。改善することのメリットや目標とか。例えば、セカンドライフのために、元気でいたい。とか、その先に目標をもつ。SEの方のように目先のことしか考えられない環境の方もおられるんですよね。あと、年令とかもあるかもしれません。
症例3) 朝食代わりに、血糖降下薬を飲んでいた・・
新良: 実は、針が嫌いな人というのが年に1〜2人位はいらしゃいます。刺した痛みというものや、刺している所を凝視できない、という方などさまざまです。自分で打つことを怖がっている患者さんには、私の腕に打ってデモンストレーションして見せたりもしています。やっぱり、言うだけではなくて自分でやって見せると案外効果あるんです。 ある時、針が見ることができないから自己注射は無理!という患者さんがいらっしゃって、この患者さんと面談を行いました。すると、私に思っていることを語ってくれたんです。自分がどういう信念や流儀を持って生きてきたか、大事にしていることはこういうことなんだ、と。ゆっくりとこんなに話を聞いてくれたのがとても嬉しかったそうで、「じゃあ、やってみるよ!」とやる気になったんです。 そうしたら、次回1カ月半後、HbA1c8.5%だったのが6.7%になったんですよ。で、話を聞いてみると、この患者さんに隠されていた問題点は別にあることが判明しました。インスリンは打てないから内服薬だけでの治療にしていたのですが、その方は心臓が悪くて心臓の薬も飲んでいました。朝食は食べない方だったんですが、心臓の薬を飲まなくてはならないので、今までは、朝食を食べずに血糖降下薬をがばっと飲んでいたそうなんです。よく低血糖が起きなかったなと驚きました。 患者さんが改善した点としては、この薬の飲み方を変えたのだとか。薬はご飯を食べてから飲むようにした。そして、食前のものは食前、食後のものは食後に飲むことにした。心臓の薬は別に飲むようにした。普通のことのようで、それがずっとできてなかったんですね。また、この方は60歳過ぎの独身男性なのですが、食事もカロリーをメニューから見てきちんと選ぶようにして、デザートがついてるものは人にあげるようにするといった努力も始めたのだそうです。 後で聞いたら、ドクターを驚かせるために、何ができるかを考えたらしいんです。先生に、「よくやったね!」と言わせたくて。薬の説明をよくよく見たら、「この薬、食事の前と書いてあるじゃないか!」と初めて知ったとか。よく生きてましたよね(笑)だから、薬についてもこれからは聞いていかなきゃなと思っています。
私が考える、指導で一番大切なこと
患者さんへの聞き取りは、とても大切なんですね
新良: 患者さんの中には、人生をこう考えているんだと、語り出す方もいらっしゃいます。語りを聞いてくれた御礼にこっちの話も聞いてやるよ、みたいな方も..(笑)改善点を探したり、的確なアドバイスを行うには、医療スタッフ側も、患者さんの人生にある程度踏み込んでいかないと具体的な話が進まないんですよね。ですから、患者さんから指導室でお話を伺うのは本当に大切です。数値だけで判断してレッテル貼ってしまうような形では、糖尿病の改善にはつながりません。
なぜ、糖尿病の療養指導を勉強しようと思ったのですか?
新良: 私は昔、平尾紘一先生(HECサイエンスクリニック理事長)のところで研修を受けて、糖尿病療養の世界に開眼しました。それまでの診察では、ドクターが「どうしてこんなに上がったんですか?」「やる気あるの?」と患者さんを追い詰めるような状況が多くみられたんです。患者さんに聞くと、「どんだけ怒られようが、1カ月に1回、3分間だけ黙って我慢していれば、薬をもらえる」と仰いました。下を向いて耐えている患者さんの姿を見て、そして、そんな患者さんの言葉を聞いて、何かおかしい、どうにかしたいと思ったんです。その頃、糖尿病のことをあまり勉強しておらず、どうしていいのかわからなくて、ある先生に相談しました。そうしたら、「じゃあ、平尾先生のところ行ってみれば?」と紹介され、平尾先生の病院で研修を受けることになりました。
先生の所では、年に一回、患者さんが参加する宿泊研修を行っており、患者さんの実体験を発表する会を聴講する機会がありました。その時に発表された、大学に入学してから1型糖尿病を発症したという21歳の女性の話には心打たれました。彼女が通院していた病院での診察は、糖尿病発症したての彼女に、インスリン注射打ちなさい、食事はこれはだめ、間食はだめ、等々、“○○しなくてはダメ”という指導のオンパレードだったそうです。何かこちらから相談・要求しても、あれやれこれやればっかりで、まったく話を聞いてもらえない状況。言っても何も聞いてもらえないから、だんだん彼女は何も言わなくなった、と。もうだめだと思うと、患者さんは喋らなくなるんですよね。
そんな環境で、病院も行きたくなくなり、治療も前向きに取り組めなくなってきたのだけど、「このままじゃ自分がだめになる!」と一念発起。その病院を転院し、自分で医療機関を探す中、たどり着いたのが平尾先生の所だったそうです。平尾先生は初診での開口一番、「何が一番大変なの?困っているの?何がイヤ?」とまず彼女の話を聞いてくれた。自分はインスリン注射が怖いということを正直に言えた。そしたら、先生は注射を持って「あ、これ?」と自分のお腹にぷすっと目の前で刺したそうです。「怖がらなくても、痛くないよ?大丈夫、大丈夫」と。その瞬間、「あ、この人は自分のことをわかってくれる・・」と思ったそうです。ちゃんと治療しようという気持ちになった、と。私も、その話を聞いて、「そう、ほんのその瞬間なんだよな」、患者さんの心を動かせるような指導ができたら素晴らしいなと思いました。そして、患者さんを常に理解しようという姿勢で接することの大切さ、投げかける言葉の力って本当に影響が大きいんだなと感じました。
患者さんが言うことには、ウソはないと思っています。できるできないは別として。その瞬間だけでも、そう思っていること、やろうと思っていることは事実ですから。だったら、そこを私たちが支えて応援してあげるのが、私たちの役割なんじゃないかと考えています。彼女の発表を聞いていたら、私たち医療スタッフの言動は、患者さんの人生を変えてしまう程の力を持っているんだなと、実感したんです。
何ができるか?を患者さんと一緒に考える
新良: 通勤で毎日、自転車に乗る、という目標を立てた人がいました。今までは、たまにだったけど毎日。「前はなんでたまにだったんですか?」と聞いたら「ウェアーが、、」と仰って、ウェアーを持って帰って洗わなくてはならないのが面倒だったとのこと。「じゃあ、通勤でウェアーを着て、スーツは会社に置いておくことにしましょう」という解決法を提案しました。毎日実行するには、“自転車に乗る”を目標にせず、“毎日スーツを置いておく”ことを目標にすれば、自然と毎日できる環境ができるわけです。目標を成功させるためには何が障壁となっているかを一緒に考え、その問題を解決してみる。遠くを見てばかりで失敗しているのであれば、近くでできることをまず考えてみることも大切だと思うんです。
やれって言われても人はやりませんよね。やるのは、自分で決めた時。糖尿病患者さんに限らず人間は皆そうだと思う。それは、自分としても信念ですね。だから、自分でやると決められるように仕向けてあげる、そのお手伝いを私たちがやって支えてあげたい。いいんですよ、「三日坊主」でも。三日続いたじゃない、今までやらなかったんだよね、と言ってあげたい。失敗しても再挑戦すればよいだけ。その繰り返しですから。とりあえず“やってみることに意義がある”と思います。
コーチングの研修で教わったのが、ペットボトルの水を見て、これだけしか水がないと思うか、まだこれだけ水があると思うか。捉え方で大きく違います。データの悪い方、うまくいってない患者さんは、できていない自分を探してしまう傾向がありますので、できた部分を探してほめてあげることも大切です。
こういうことは全部いろいろ教わってきたことで、やっと自分も還元して、少しずつ教えてあげられるようになってきました。平尾先生もそうですけど、私だってお菓子が好きだし、世の中にはいろんな人がいて、それがたまたま糖尿病をもったんだから、めがねをかけるのと一緒で上手にやって楽しくいこうよという姿勢でポジティブに患者さんと取り組むことを信条にしています。平尾先生みたいにどっしり構えて、「こうやってやってけばいいんじゃない?」と、肩をポンと叩いてくれるような医療者が私の理想です。ずっと、そんな感じでいたいなと思います。そんな、患者さんにやさしい環境がもっともっと広がっていくことを心から願っています。
糖尿病療養指導での間食指導とは
今回、間食指導というテーマではありましたが、糖尿病療養指導という広い括りの中で、患者さんをどのように導き、やる気を出して療養生活を送っていただけるかを、私の経験を含めてお話しました。間食をどうしたらやめられるか、減らせるか、、というだけのことではなく、患者さんが間食に走る原因は何なのか、それをどう解決していけるかを、医療スタッフは時間をかけて患者さんと一緒に考えていくことが、本当に大事だと考えています。
<今日のまとめ> 間食指導「私の3カ条」
- 患者さんが言うことにウソはない
〜言った瞬間だけでも、そう思ったことは事実ですから。 - 三日坊主でも三日続いたなら全然OK!実行することに意義がある。
〜できなかった部分を探すのではなく、できた部分を探してほめること。 - 私たち医療スタッフの言動は、患者さんの人生を変える
〜患者さんの生活の中で大切にしていることや、状況、環境など、あらゆる方向から考えながら、
提案や情報提供を行う。
【 Profile 】
新良啓子さん
関東労災病院に長年勤務。
2002年糖尿病療養指導士(CDEJ)
2003年糖尿病看護認定看護師 看護外来開設
2005年脳神経外科・形成外科、皮膚科病棟師長
2007年外来師長
新良啓子さん
関東労災病院に長年勤務。
2002年糖尿病療養指導士(CDEJ)
2003年糖尿病看護認定看護師 看護外来開設
2005年脳神経外科・形成外科、皮膚科病棟師長
2007年外来師長